内容説明
文字・活字文化の継承に向けた、経済界随一の読書家からの提言。
目次
第1章 私の読書体験
第2章 読書と教養
第3章 仕事は読書によって磨かれる
第4章 私が影響を受けてきた本
第5章 読書と日本人
第6章 出版・活字文化の大いなる課題
著者等紹介
福原義春[フクハラヨシハル]
1931年東京生まれ。1953年慶応義塾大学経済学部卒業後、資生堂入社。米国法人社長を経て、商品開発部長、取締役外国部長。フランス、ドイツに現地法人を設立、中国に進出するなど海外市場拡大戦略を推進した。1987年第十代代表取締役社長。1997年代表取締役会長。2001年名誉会長。東京都写真美術館館長、文字・活字文化推進機構会長、企業メセナ協議会会長、日仏経済人クラブ日本側議長、日伊ビジネスグループ日本側議長、東京芸術文化評議会会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
14
経営者であるとともに読書家である福原さんの読書論です。ノウハウ的な本は読まずにやはり古典など考えさせる本をよく読まれています。読書に対する姿勢というものが書かれていて参考になります。2013/12/28
kubottar
9
オフィスに1000冊、ご自宅には2万冊の本があるという資生堂名誉会長福原義春氏の本。本を能動的に読む為には、数千年という時代のフィルターにさらされて生き残った古典を積極的に読まなければならない。ガリア戦記、一度挫折したけどまた読んでみるかな2012/03/22
ともこ
7
書店で装丁や帯に惹かれ手にしたものの、期待に反し途中で投げ出したくなる本がいかに多いことか。最近、しばしば著者と同じ思いをします。「人がいかに生き、死と向かい合ったかを学ぶ」それを知ることができるのは、今なお生き残っている古典の力が大きいとも。先人の遺産ともいえる古典、現代の世相をうかがえる話題の書物、両輪の読書を心掛けたいと思いました。やなせたかしさんの「アンパンマンのマーチ」の引用はまさに的を射ています。「なんのために生まれてなにをして生きるのか」それを探る手掛かりとして読書を続けたいです。2017/02/22
maito/まいと
7
良くも悪くも一流の読書家の文章だなあ、と思う1冊。他文化に精通した書評や日本文化に対する視点、これからの価値観の変化、何より出版(書店)業界に対する提言は頷けるモノばかり。が、本筋である「本を読む」必要性や本の重要性については、それほど心を動かされなかった。活字文化の廃化や、本が読まれないことが課題、という設定は正直古い(中高年の方が活字から遠ざかっているというデータすらある)。必要性を実体験だけでなく(それこそ)今やこれからの日本の情勢を盛り込んでくれれば、もっと理解が深まったのに、と残念に思った。2010/10/29
サラダ
6
著者は資生堂名誉会長です。「私という人間は今まで読んだ本を編集してでき上がっているのかもしれない」が記憶に残りました。紹介されていた本は挫折しそうな(挫折した)ものが多かったですが、その中で、人生の真理が書かれていると解説されていた「ご冗談でしょう、ファインマンさん」、「悪童日記」の2冊を読んでみようと思います。2018/09/20
-
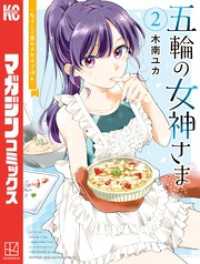
- 電子書籍
- 五輪の女神さま ~なでしこ寮のメダルご…







