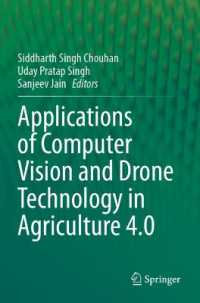- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 学校・学級経営
- > 学校・学級経営その他
出版社内容情報
中教審の教育課程部会「論点整理」をはじめとして、総則・評価特別部会「検討資料」、ワーキンググループの資料などに基づき、2030年に実施される次期学習指導要領改訂に係る「最新の審議内容」を徹底解説!
「高次の資質・能力(中核的な概念等)」「情報活用能力」「探究的な学び」「調整授業時数制度」「裁量的な時間」「総合・情報領域」「脱『教科書網羅主義』」「高校入試の在り方」など、教育関係者必見の1冊!
本書の概要
2024年12月に行われた中教審への諮問を受けて、次期学習指導要領の改訂審議が進んでいます。そこで本書では、教育課程部会「論点整理」(2025年9月25日)だけでなく、総則・評価特別部会「検討資料:目標・内容の構造化・表形式化等」(10月14日)など、「次期学習指導要領改訂に係る最新の審議内容」をわかりやすく解説します。
2025年10月14日に公表された総則・評価特別部会「検討資料:目標・内容の構造化・表形式化等」によると、「論点整理」において「中核的な概念等」とされていた用語が、「高次の資質・能力」(「知識及び技能に関する統合的な理解」と「思考力、判断力、表現力等の総合的な発揮」の総称)に改められています。
これは、「新たな用語の提起には慎重であるべきとの指摘もあり、現行との連続性を感じられる書きぶりとすることが重要」との判断からなされたものですが、単なる用語の変更にとどまるものではありません。
端的に言えば、現行学習指導要領における「資質・能力」との関連がわかりにくかった「中核的な概念等」を「高次の資質・能力」とすることで、「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力等」との関係性を明確にしたものだと言えます。
このことからもわかるように、9月に公表された「論点整理」を読み解くことに加えて、その後どのようなことが審議されているか「最新の審議内容」も併せて読み解くことが、次期学習指導要領の改訂内容をより深く理解するうえで欠かせないということです。
そこで本書は、そうした最新情報を盛り込みながら、以下に挙げる「40の核心テーマ(Question)」に基づいて徹底解説します。
【目次】
〈プロローグ〉2030年実施の学習指導要領が示唆する「四つの決別」
第Ⅰ部 学習指導要領改訂の基本方向を探る
[Question 01]次期学習指導要領の「核となるテーマ」は何か
[Question 02]次期学習指導要領では、どのような人材育成が目指されているのか
[Question 03]「主体的・対話的で深い学び」は「個別最適・協働的な学び」に置き換わるものなのか
[Question 04]これからも「資質・能力」ベースの学習指導要領となるのか
[Question 05]カリキュラムをマネジメントするむずかしさを乗り越えられるか
[Question 06]「多様性の包摂」とは、具体的にどのようなことを意味するのか
[Question 07]「実現可能性の確保」という言葉が意味することは何か
第Ⅱ部 次期学習指導要領改訂の特色
[Question 08]現行の学習指導要領はなぜ、「使いにくい」と言われているのか
[Question 09]学習指導要領の規定を表組みにすると、かえってわかりにくくなってしまうのではないか
[Question 10]「高次の資質・能力」(中核的な概念等)とはどのようなものか
[Question 11]教育内容が精選されれば、本当に教える量が減るのか
[Question 12]各教科等における「見方・考え方」は次の改訂でも重視されるのか
[Question 13]学習評価の観点である「主体的に学習に取り組む態度」がなくなるというのは本当か
[Question 14]デジタル学習指導要領とは何か
[Question 15]デジタル端末の活用はいままでどおりでよいか
第Ⅲ部 多様性を包摂する柔軟な教育課程とは何か
[Question 16]新たに「調整授業時数制度」「裁量の時間」が設けられる意図は何か
[Question 17]新設される「調整授業時数制度」とは具体的にどのような制度か
[Question 18]新設される「裁量的な時間」とは具体的にどのような時間か
[Question 19]複層的に包摂する「2階建て」の教育課程とは何か
[Question 20]不登校の子どもたちの学びはどのように保障されるか
[Question 21]いわゆる「ギフテッド」を対象とする教育課程はどのようなものになるか
[Question 22]日本語指導が必要な子どもたちの学びはどのように保障されるか
第Ⅳ部 学びの新たな柱─「情報活用能力」と「探究」
[Question 23]いま、改めて「情報活用能力」が強調されているのはなぜか
[Question 24]「情報活用能力」とは具体的にどのような能力か
[Question 25]日本の子どもの「情報活用能力」にはどのような課題があるのか
[Question 26]小学校「総合的な学習の時間
内容説明
40の革新テーマ。
目次
プロローグ 2030年実施の学習指導要領が示唆する「四つの決別」
第1部 学習指導要領改訂の基本方向を探る
第2部 次期学習指導要領改訂の屋台骨
第3部 多様性を包摂する柔軟な教育課程
第4部 学びの新たな柱―「情報活用能力」と「探究」
第5部 教育改革を支える条件整備
第6部 次期学習指導要領における教員の役割
エピローグ もつべきは「150年に1回」の大改訂という意識
著者等紹介
佐藤明彦[サトウアキヒコ]
教育ジャーナリスト。1972年生。滋賀県出身、東北大学教育学部卒、大手出版社勤務を経てフリーの記者となり、2002年に編集プロダクション・株式会社コンテクストを設立。教育書の企画・編集に携わる傍ら、自身は教育分野の専門誌等に記事を寄稿。教員採用試験対策講座「ぷらすわん研修会」の事務局長、『月刊教員養成セミナー』元編集長を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あみやけ
settar
epitaph3
ジーフー
Go Extreme