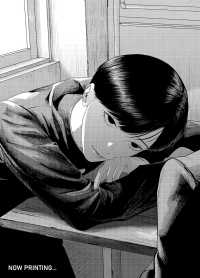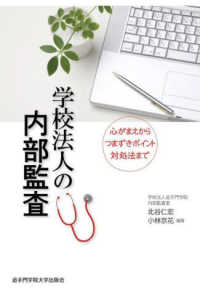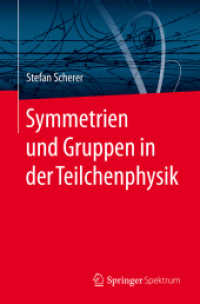出版社内容情報
本書の概要
授業において「討論」は非常に難しい。いわば、教師が憧れを持つ授業形態とも言える。その難しさに25年間挑戦してきた著者が、代表教材9本の実践を解説する。令和型の討論を提案するだけでなく、発問集なども惜しみなく書き記した骨太な国語の教育書である。
本書からわかること
・憧れの討論の授業
討論の授業は、子どもが自分の考えを言葉にし、仲間の意見に耳を傾けながら思考を深めていく学びである。たくさん話し、たくさん聞き、しっかり読み、たくさん書き、しっかり考える。その積み重ねの中で、子どもは自分の言葉で世界をとらえ、他者とともに新しい考えを生み出していく。著者の25年におよぶ「討論の授業」の集大成。
・代表的な教材を完全網羅使える実践事例!
国語授業での代表教材を網羅。
討論の授業にかかわらず、授業づくりに役立つ1冊。
1年生 大きなかぶ
1年生 たぬきの糸車
2年生 スイミー
2年生 お手紙
3年生 モチモチの木
4年生 ごんぎつね
5年生 大造じいさんとガン
6年生 やまなし
6年生 海の命
こんな先生におすすめ
・討論の授業に挑戦したい先生
・授業実践をワンランクレベルアップしたい先生
・国語の代表的な教材を学びたい先生
【目次】
第1章 令和型討論の授業の提案
討論の授業とは何か
(1)様々なタイプの討論の授業
(2)教員人生を変えた憧れの討論‾向山洋一氏の「やまなし」実践‾
(3)討論の授業で身に付く力
(4)令和型討論の授業の誕生
令和型討論の授業の基本モデル
(1)学習問題の提示【教師の発問】
(2)自力解決【ノートに考えを書く】
(3)集団思考【討論をする】
(4)討論の再構成【ノートにまとめる】
第2章 令和型討論の授業のつくり方
討論の授業を核にした単元づくり
(1)教材との出会い初発の感想の書かせ方
(2)文章の理解を支える音読のさせ方
(3)語彙力を高める辞書引き競争
(4)あらすじをつかませる授業「シーケンスチャート法」
(5)討論による学習問題の追究
討論の授業を成功に導く7つの指導場面
(1)討論の目的を共有する
(2)初めての「指名なし発表」の指導
(3) 「指名なし発表」の質を高める指導
(4)初めての「指名なし討論」の指導
(5) 「指名なし討論」の質を高める指導
(6)身に付ける力を明確化する「討論マスターカード」
(7)子どものモチベーションを高める指導
第3章 令和型討論ができる学級をつくる4月の指導
授業開き教科書扉の詩で指導すること
(1)学習で一番大切なことは「聞くこと」
(2)初めての音読と視写
(3)2回目の国語の授業で、すぐ討論
最初の物語教材で、討論の基礎を習得する(教材「白いぼうし」 )
(1)松井さんが白いぼうしの中に夏みかんを入れたことに賛成か、反対か
(2)消えた女の子の正体は何か
(3) 「白いぼうし」という題名に賛成か、反対か
第4章 学年別有名教材令和型討論の実践例
1年生大きなかぶ
(1)討論前の音読発表会‾音読の工夫を教える‾
(2)教科書と絵本、どちらがよいか
1年生 たぬきの糸車
(1)主役は誰か
(2)おかみさんの気持ちが変わったのは、どこか
(3)たぬきは、また来るか
2年生スイミー
(1)スイミーは、どんな魚か
(2)スイミーのあらすじ
(3)スイミーは、どうして目になることができたのか
2年生 お手紙
(1)がまくんとかえるくん、どちらが主役か
(2)がまくんの気持ちが、最も変わったのはどこか
(3)かえるくんは、お手紙の内容を伝えてよかったのか
3年生 モチモチの木
(1)豆太の気持ちが変わったのは、どこか
(2)豆太は、勇気のある子になれたのか
(3) 「モチモチの木」の主題(テーマ)は、何か
4年生 ごんぎつね
(1)ごんは、どんなきつねか
(2)ごんは、
内容説明
著者の25年におよぶ「討論の授業」の集大成。代表的な教材を完全網羅。憧れの授業を、あなたの教室で。むずかしさの先に、子どもの「本気」がある。たくさん話す。たくさん聞く。しっかり読む。たくさん書く。しっかり考える。国語の授業はもっともっと楽しくなる。
目次
1 令和型討論の授業の提案(討論の授業とは何か;令和型討論の授業の基本モデル)
2 令和型討論の授業のつくり方(討論の授業を核にした単元づくり;討論の授業を成功に導く 7つの指導場面)
3 令和型討論ができる学級をつくる 4月の指導(授業開き 教科書扉の詩で指導すること;最初の物語教材で、討論の基礎を習得する(教材「白いぼうし」))
4 学年別 有名教材 令和型討論の実践例(1年生 大きなかぶ;1年生 たぬきの糸車;2年生 スイミー;2年生 お手紙;3年生 モチモチの木;4年生 ごんぎつね;5年生 大造じいさんとガン;6年生 やまなし;6年生 海の命)
5 令和型討論ができる 学年別発問集(1年生 はなのみち/おむすびころりんんやくそく/くじらぐも/おかゆのおなべ/ずうっと、ずっと、大すきだよ;2年生 ふきのとう/お手紙/スーホの白い馬;3年生 春風をたどって/まいごのかぎ/ちいちやんのかげおくり/三年とうげ;4年生 一つの花/友情のかべ新聞/スワンレイクのほとりで;5年生 銀色の裏地/たずねびと/やなせたかし―アンパンマンの勇気/たずねびと;6年生 帰り道/ぼくのブックウーマン)
著者等紹介
武田晃治[タケダコウジ]
神奈川県公立学校教諭。横浜国立大学教育学部卒(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
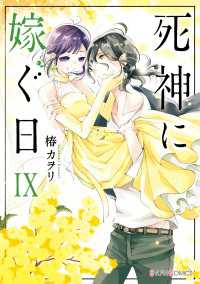
- 電子書籍
- 死神に嫁ぐ日IX【電子限定特典付き】 …
-

- 電子書籍
- 七緒 2015 秋号vol.43