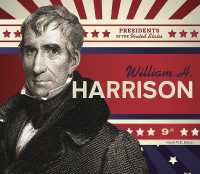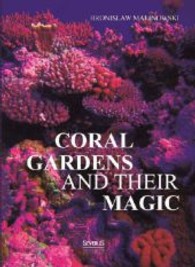出版社内容情報
本書の概要
教科の価値、知識・技能の総合的理解、個別最適な学びと協働的な学び、数学的表現、新たな単元構成…。これまでの算数授業と一線を画した内容が詰まった事例&解説! 真の能力ベイスの授業がここにある!!
本書からわかること
次期学習指導要領に向けて算数科で考えていくべきこと
現在、中教審では次期基準策定に向けた議論が活発に進められ、算数科・数学科においてもこれまで能力ベイスの授業づくりを継承していくことが打ち出されています。深い学びの充実、見方・考え方と資質・能力
【目次】
はじめに
第1 章 論説
いかに数学的な授業を創るか
第2 章 実践事例
A 教科の価値の自覚化を目指す授業展開の在り方
1 乗除法の関係に着目した倍概念育成のための
授業デザイン
第3 学年:倍の計算
2 「速さ」を通して考える関数の学びとその新しい価値
第5 学年:速さ(関数)
B 高次の資質・能力の獲得に向けた単元の在り方
3 倍概念の獲得に向けた単元構成
第2 学年:倍の意味
4 中核的な概念の形
内容説明
教科の価値、高次の資質・能力、個別最適な学びと協働的な学び、数学的表現、新たな単元構成…。2030年実施の学習指導要領を見据えた9つのテーマをもとに圧倒の23事例を掲載!
目次
第1章 論説 いかに数学的な授業を創るか
第2章 実践事例(教科の価値の自覚化を目指す授業展開の在り方;高次の資質・能力の獲得に向けた単元の在り方;カリキュラム・オーバーロードの解消を目指す基準性の捉え方;個別最適な学びの実現に向けた教材研究の進め方;豊かな人間性の構築を図る協働的な学び;数学的コミュニケーションの充実を図る数学的表現の価値;学年・領域を超えた汎用性のある能力獲得を目指す単元開発;領域構成の主旨を踏まえた新しい単元構成;情報伝達・共有のパラダイムの転換と算数の授業)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme