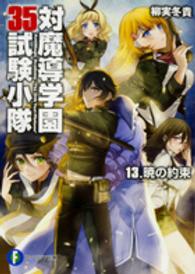- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 教科指導
- > 情報・コンピュータ教育
出版社内容情報
本書の概要
1人1台端末やクラウド環境といったデジタル学習基盤が整備された現在、児童生徒に育てるべきは情報活用能力である。本書では、「デジタル学習基盤」や「情報活用能力」についての基本事項をふまえた上で、情報活用能力を育成するための実践例を紹介する。
本書からわかること
そもそも「情報活用能力」とは?
「情報活用能力」は、現行の学習指導要領解説では「世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力」と定義されています。
「言語能力」「問題発見・解決能力」と共に学習の基盤となる資質・能力と位置づけられ、教科等を限定することなく育成することが求められています。
「情報活用能力」の要素
文部科学省(2019)は「情報活用能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの在り方と授業デザイン―平成30年度 情報教育推進校(IE-School)の取組より―」で、「A. 知識及び技能」「B. 思考力、判断力、表現力等」「C. 学びに向かう力、人間性等」に沿って「情報活用能力」の要素を分類しています。
A. 知識及び技能
1 情報と情報技術を適切に活用するための知識と技能
2 問題解決・探究における情報活用の方法の理解
3 情報モラル・情報セキュリティなどについての理解
B. 思考力、判断力、表現力等
1 問題解決・探究における情報を活用する力(プログラミング的思考・情報モラル・情報セキュリティを含む)
C. 学びに向かう力、人間性等
1 問題解決・探究における情報活用の態度
2 情報モラル・情報セキュリティなどについての態度
「情報活用能力」と聞くと上記のA-2やB-1などを思い浮かべがちですが、端末の基本的な操作を習得することや、情報モラル・情報セキュリティについての理解や態度などについても育成が求められています。
「情報活用能力」を育てるには?
前述のとおり、「情報活用能力」は特定の教科や時間の中だけで育成するわけではありません。
では、たとえば、端末を使用する上で基本となるキーボード入力などは、どんな時間に、どのように指導するとよいでしょうか?
また、情報活用とは、探究的な学びの中にどのように位置づけられるのでしょうか?
さらには、情報モラル・情報セキュリティについてはどうでしょうか?
どの時間、どの教科で教えてもよい(あるいは、どの時間、どの教科でも教えるべきである)からこそ、指導に難しさもあると思われます。
【目次】
まえがき
Ⅰ 学習の基盤となる情報活用能力
今日の情報活用能力はどのようにして構築されてきたか
1人1台端末時代に求められる「情報活用能力」とは
情報活用能力を授業でどのように育てていくか
ICTを普段使いするためのコツ
Ⅱ 情報活用能力を育てる実践
1 探究的な学習の基盤
1-1 情報の収集
学習の基盤となる情報収集のコツ
教科書から必要な情報を抜き出す
二次元コードを使った情報収集
番組構成をヒントにした情報収集
体験活動で情報収集する力を育む
教科の学びのつながりを意識した情報収集
情報収集の技能の計画的な育成
1-2 整理・分析
情報を整理・分析するためのはじめの一歩
教科書を使った探究的な学習の段階的な指導
考えの種「~かも」をつくる
教科の見方・考え方を働かせた整理・分析
探究的な学習におけるテキストの分析
説得力のある伝え方を身に付ける
情報活用能力を基盤とした自己調整力の育成
自らの学習課題を立て,解決の手順を考える
単元の学びを可視化し,付けた力のメタ認知へ
総合的な学習の時間での情報活用能力の発揮
1-3 まとめ・表現
「数と式」領域における解法の説明
相手に合わせて言葉を変える
情報活用を評価・改善する高め合いの協働
相手意識をもったポスター作成
発信力を高めるための動画での振り返り
解説 探究的な学習の基盤としての情報活用能力
2 ICT活用
2-1 基本的な操作等
キーボード入力スキルの向上
ショートカットキーのスキル練習
基本的な操作スキルの継続的な育成
授業内での基礎的な操作等の習得
2-2 クラウドの活用
体験を通したクラウドの特性の理解
クラウド環境での基本的な操作等の習得
共有された友達の情報を大切にしよう
「情報活用能力チェックシート」の活用
学習状況を共有し,協働的な学びの価値に気付く
解説 クラウド環境を活用する中で実現したいこと
3 情報・メディア
3-1 情報技術・プログラミング
より洗練された成果物を作成するための生成AIの活用
プログラミングを試しながら表したいことを考える
エネルギーを効率よく使うためのプログラミング体験
SDGsの視点から考えるプログラミング
3-2 メディアリテラシー
授業の中で生成AIを学ぶ
ニュース記事を事実と意見に分ける
紙の新聞と新聞社のウェブページを比べる
情報を批判的に分析しようとする態度の育成
生成AIが生成した情報を読み解く
見る・創る・活かす! 映像活用スキル育成プロジェクト
「虚構新聞」を読んで書く
解説 情報・メディア・技術のリテラシー
4 情報モラル・情報セキュリ
目次
1 学習の基盤となる情報活用能力(今日の情報活用能力はどのようにして構築されてきたか;1人1台端末時代に求められる「情報活用能力」とは;情報活用能力を授業でどのように育てていくか;ICTを普段使いするためのコツ)
2 情報活用能力を育てる実践(探究的な学習の基盤;ICT活用;情報・メディア;情報モラル・情報セキュリティ;研修)
著者等紹介
佐藤和紀[サトウカズノリ]
信州大学学術研究院教育学系准教授。1980年生まれ。東北大学大学院情報科学研究科修了、博士(情報科学)。東京都公立小学校、常葉大学専任講師等を経て現職。文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する検討会議」委員、文部科学省初等中等教育局視学委員等
三井一希[ミツイカズキ]
山梨大学教育学部准教授。1982年生まれ。熊本大学大学院教授システム学専攻博士後期課程修了、博士(学術)。山梨県公立小学校、常葉大学専任講師等を経て現職。文部科学省学校DX戦略アドバイザー、熊本大学教授システム学研究センター連携研究員等
泰山裕[タイザンユウ]
中京大学教養教育研究院教授。1984年生まれ。関西大学大学院情報科学研究科博士課程後期修了、博士(情報学)。鳴門教育大学准教授等を経て現職。文部科学省「情報活用能力調査の今後の在り方に関する調査 調査枠組等委員会」委員、同「評価規準、評価方法等の工夫改善に関する調査(中学校総合的な学習の時間)」研究協力者等(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
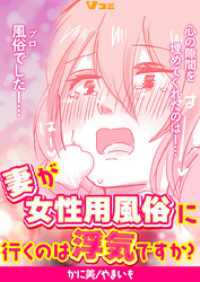
- 電子書籍
- 妻が女性用風俗に行くのは浮気ですか?8…
-
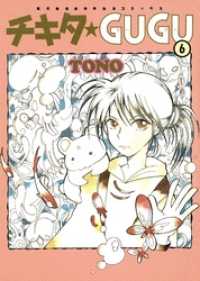
- 電子書籍
- チキタ★GUGU 6巻 眠れぬ夜の奇妙…