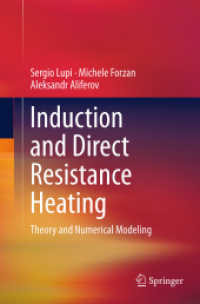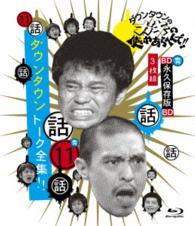出版社内容情報
中教審への諮問を受け、学校現場からの声を届ける!
〈本書の概要〉
2024年12月25日に、中央教育審議会へ諮問が出され、いよいよ学習指導要領改訂へ向け、動きが活発になってきました。本書は、日々学校で子どもたち、授業と向き合う著者が、常に子どもの事実から考える教育観に基づき、学習指導要領改訂のキーワードの「意味」を捉え直していきます。
〈本書からわかること〉
・「その子が学ぶ」という教育の本質を知る
時代によって主体性、子ども中心、自ら学ぶなど、言い方は様々に変化してきましたが、その中身は変わりません。しかし、こうした変化の節目には、我々教師の周りに実に多くの新しいキーワードが登場します。ウェルビーイング、エージェンシー、自由進度学習、個別最適な学び、教育DX…。そして、これらの解釈と具現化を巡って多くの実践と研究が行われます。ただ、履き違えてはいけないのは、これらのキーワードは「その子が学ぶ」という教育の本質と切り離してはいけないということです。
学習指導要領の改訂に向けて、新しいキーワードと教育の本質がどのように結び付くのか、その視点を読者の方と一緒に考えたいというのが、本書の目的です。
・先生のため、子どものための働き方改革を
「働き方改革」という言葉が随分浸透してきました。しかし、学校現場では、なかなか思うように進んでいないのが現状でしょう。また、労働時間だけの問題ではなく、いじめ、不登校、保護者対応など複雑な問題が山積していることから、教師の「多忙感」が改善されないことも問題であると感じます。
* * *
次期学習指導要領への16の提言
提言1 教師自身が主体を取り戻す
提言2 目の前の子どもにとっての「意味」を考える
提言3 これまでの当たり前を捨てる
提言4 子どもが恩恵を受けられる働き方改革を
提言5 自身の教育観を見つめ直す
提言6 その子の世界観から見る(子ども観)
提言7 子どもの事実から不登校を考える(子ども観)
提言8 子どもはどのように学ぶのか考える(授業観)
提言9 知識を教えることは悪いことではない(学力観)
提言10 教師としてやるべきこと、あえて行わないことを整理する
提言11 デジタルのメリットとデメリットを考える
提言12 常に子どもの事実から授業を創造する
提言13 見取りの力なくして個別最適な学びなし
提言14 文化は創り出すもの
提言15 主任教諭に具体的な役割を示す
提言16 保護者の教育観を転換する。
〈こんな先生におすすめ〉
・子ども主体の学びを実践したい先生
・学習指導要領改訂の方向性を知りたい先生
・学校文化を変えたいと思っている先生・管理職
・小学校教諭、中学校教師、管理職
内容説明
文部科学大臣による諮問を受け、子どもの学びと授業の姿を考える!改訂のキーワードの裏側に隠された「意味」を捉える!
目次
第1章 教師自身の主体性(教師自身が主体性を取り戻す;目の前の子どもにとっての「意味」を考える ほか)
第2章 教育観の転換こそが急務(自身の教育観を見つめ直す;その子の世界観から見る(子ども観) ほか)
第3章 授業をどのように創るか(教師としてやるべきこと、あえて行わないことを整理する;デジタルのメリットとデメリットを考える ほか)
第4章 学校文化を変える(文化は創り出すもの;主任教諭に具体的な役割を示す ほか)
著者等紹介
齊藤慎一[サイトウシンイチ]
東京都公立小学校副校長。昭和55年東京都生まれ。都内複数の小学校教員を17年間勤めて現職。平成30年度東京都派遣教員として東京学芸大学教職大学院へ。学習者中心の学びとそれに伴う教師の教育観の研究を行う。全国複数の学校で講師を務める。日本学校教育学会会員、体育授業研究会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。