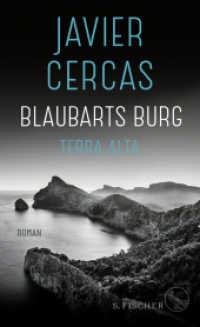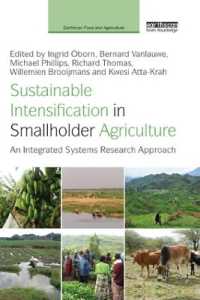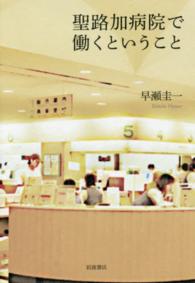出版社内容情報
価値提供の視点を変革していかなければならない。
新時代の「普段」の授業を変え、教室の雰囲気を一変させる。
本書の概要
子どもたちが「学び手」の時代に、教師は何ができるのか。令和時代の普段の授業とはどうあるべきか。全79個の「学ぶ力」を育む教師のアクションプランを提案!
本書からわかること
学校で鍛えることができる7つの力・79のアクション
生涯にわたって使える「学ぶ力」を、小中学校の教室から培うことができる。その学ぶ力を7つに分類し、79の超具体のアクションを解説する。
①学習者として考える力
②計画を立てる力
③目標を設定し、運用する力
④集中する力
⑤継続する力
⑥振り返り・メタ認知の力
⑦協働する力
「学び方を学ぶ」ために大切なことは?
本書を執筆するにあたり、「学び方・学ぶ力」に関する100冊以上の本を読み、20本以上の動画を視聴。100冊において、最頻出のキーワードは「習慣」。「学級の習慣」に着目したこれまでにない新提案で、教室が大きく変わる。
こんな先生におすすめ
・教室で、学ぶ力もレベルアップさせたい方
・これまでの学級づくり、授業づくりを打破したい方
・自由進度学習のベースとなる学級づくりに関心のある方
内容説明
学校で鍛えることができる7つの力・79のアクション。学習者として考える力/計画を立てる力/目標を設定し、運用する力/集中する力/継続する力/振り返り・メタ認知の力/協働する力。価値提供の視点を変革していかなければならない。新時代の「普段」の授業を変え、教室の雰囲気を一変させる。
目次
第1章 学習者の考え方・マインドを学ぶ授業
第2章 計画を立てる力を学ぶ授業
第3章 目標を設定し、運用する力を学ぶ授業
第4章 集中する力を学ぶ授業
第5章 継続する力を学ぶ授業
第6章 振り返り・メタ認知の力を学ぶ授業
第7章 協働する力を学ぶ授業
著者等紹介
難波駿[ナンバシュン]
1988年北海道富良野市生まれ。北海道札幌国際情報高等学校卒。北海道教育大学札幌校卒。同年より札幌市公立小学校にて勤務。札幌市教育研究推進事業国語科副部長。北海道国語教育連盟説明文部会チーフ。子どもが「勉強って楽しい、学ぶって面白い」と感じる授業を目指し研究中。学習者主体の授業手法や教育観、自立した子の育成に関する発信を書籍・講演会・SNSを通して続けている。2023年3月に著書「超具体!自由進度学習はじめの一歩」(東洋館出版社)を出版。同書は発売から重版を積み重ね、ベストセラーとなっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のぶのぶ
かるろ
ジーフー
Go Extreme
こーじ