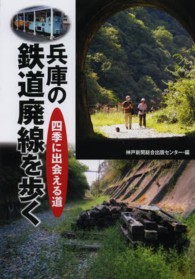出版社内容情報
「古書」は先人との出会いであり、先人との対話である。
古書をめくるその手には、先人の知恵と未来への願いが宿る。
歴史に残る社会科実践を追究する。
前作『社会科教材の追究』の続編。今回は、厳選された22冊の「古書」を学びの種として、歴史に残る「社会科実践」を取り上げて解説します。古書を通じて、社会科教育とは何か、社会科授業とは何かについて言及した一冊です。
◎社会科の王道
古書を読み解くことは、教育者としての鋭敏な観察力や深化する学びの姿勢を育む機会であり、過去の知恵との対話から、現代の教育課題に新たな洞察をもたらす機会でもあります。本書では、古書を理解し、実践に活かすためのアプローチや方法を提案します。内容は「本書について」「本書の価値」「本書から得た学び」という構成になっています。古書の概要や,執筆者がどこに価値を見出したのか,どのような学びを得て何をどのように今に受け継ぐべきかなどを詳細に述べています。これによって,古書のどの部分をどのように授業や実践に活かせるのかを明らかにします。
社会科教師の方にとって、必読書と言えます。
◎厳選された名著の旅
名著を切り口に、戦後から現在に至るまでの社会科教育を俯瞰し、今なお、その圧倒的な熱量を肌で感じ取ることができます。「初期社会科」「授業実践」「方法論」「内容論」といったシーンを分類し、社会科教育の壮大な旅を体験できます。
こんな人におすすめ
・社会科教育のこれまでの歴史を知りたいという先生
・授業をもう一歩深みのあるものにしたいという先生
・社会科教師として、胸を張って実践を語りたいという先生
内容説明
歴史に残る社会科実践を追究する。古書をめくるその手には、先人の知恵と未来への願いが宿る。「古書」は先人との出会いであり、先人との対話である。厳選された22の古書から学び、新たな実践を見出す!
目次
第1章 「古書」をとらえる構え(古書を教師が探究する意義;古書を辿る旅―古書の見方・読み方・考え方)
第2章 「古書」から得る22の学びの種(初期社会科;授業実践;方法論;内容論;子ども理解)
巻末
著者等紹介
佐藤正寿[サトウマサトシ]
東北学院大学文学部教育学科教授
宗實直樹[ムネザネナオキ]
関西学院初等部教諭
石元周作[イシモトシュウサク]
大阪市立野田小学校教頭
中村祐哉[ナカムラユウヤ]
広島県安芸郡熊野町立熊野第一小学校教諭。広島大学大学院人間社会科学研究科在籍
近江祐一[オウミユウイチ]
岡山県教育委員会岡山教育事務所指導主事(主任)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あべし