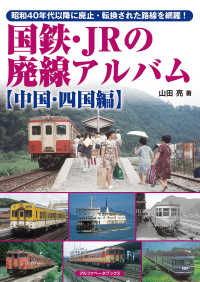出版社内容情報
生徒の見取り、つながり方を解説
生徒一人ひとりを満たすための学級づくりを提案!
本書の概要
中学校の担任の先生は、朝からずっと生徒のそばにいるわけではありません。忙しい現場では尚更。したがって、限られた時間の中で、教師から関わっていく技術をたくさんもつことが必要です。本書では、生徒をどのように見取り、かかわりを増やしていけばいいのか。生徒一人ひとりを満たすための学級づくりを提案します。
本書からわかること
生徒の適切な見取り
教師がどのように行動するかの根本には、見方や考え方が存在します。生徒の見取りを誤れば、かかわり方がおかしくなってしまいます。特に、中学生という発達段階を加味した見方をもち、適切な関わりをもつことが求められます。生徒の見方の勘所を解説します。
生徒との関わりを増やす技術
生徒とつながり方、かかわり方を「個人」と「集団」の観点から解説します。一人ひとりが満たされていくことで、互いに認め合える集団としてまとまりが生まれます。そして、集団のまとまりが、さらに一人ひとりを満たされていきます。「自分は認められている」「自分のことをわかってくれている」。そう生徒が感じるようなアプローチを紹介します。
こんな先生におすすめ
・これからはじめて中学校で担任をもつという方
・中学校の学級経営で悩んでいる方
内容説明
限られた時間の中で生徒とのかかわりを増やす。自分は認められている、自分のことをわかってくれている。一人ひとりを満たすための学級づくり。見方とかかわり方で変わる「個」と「集団」へのアプローチ。
目次
第1章 生徒の見方(○○な部分もあれば、△△な部分もある;成長は「今」でなくてもいい ほか)
第2章 生徒とのかかわりを増やす方法(何を自己開示するか;生徒の世界に足を踏み入れる ほか)
第3章 一人ひとりを満たすための個へのアプローチ(情報源はたくさんある;好きになろうとするから好きになる ほか)
第4章 一人ひとりを満たすための集団へのアプローチ(学級は担任の理想の場ではない;なぜシステムをつくるのか ほか)
著者等紹介
北村凌[キタムラリョウ]
1993年、和歌山県和歌山市生まれ。2015年和歌山大学卒業。和歌山県公立中学校勤務9年目。初任者時代に和歌山大学教職大学院の「初任者研修履修証明プログラム」に参加し、学び続ける教師の土台を築く。その後も様々なセミナーや書籍を通じて学びつつ、自身でもサークル活動を行って研鑽を重ねている。「その生徒にとって必要な成長とは何か」がモットー。雑誌原稿の他、国語科の授業に関する論文を複数執筆。わかやま子ども学総合研究センター特別研究会員。日本国語教育学会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- こどもと遊ぶ!首都圏の遊び場ベストガイ…