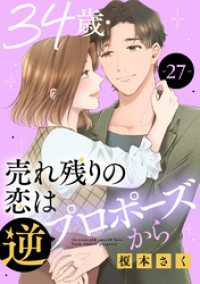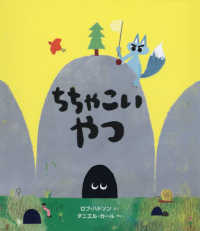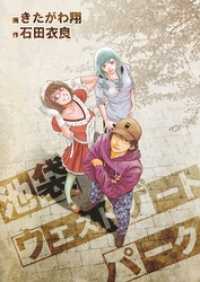出版社内容情報
「常識」には疑い方がある――
地道に成果をあげ続ける、土居正博先生の実践改善の裏側が丸わかり!
本書の概要
思考停止で前例踏襲の授業にも、「奇をてらう」だけの授業にも陥らない、地に足のついた実践改善の方法
●ぼんやりと存在している「常識」を見つける「目」が手に入る
●「常識」に気づいたときにすべきことが分かる
●多忙でも持続可能な実践改善の習慣が身につく
●土居先生の国語授業の「常識」の乗り越え方を追体験できる
だれでも、どの教室でもできる、ほんの少しの工夫で大きな効果を生みだす実践の創り方を提案します。
本書からわかること
そもそも「常識」ってなんですか?
――「常識を疑え」を考える
「これまでの常識はもう通用しない」「常識に縛られず、自由に考えて行動しよう」「常識を疑って、新しいものを生みだそう」……。
変化する社会に対応した学校づくりや授業改善が求められる中で、このような言葉を耳にする機会も増えているのではないでしょうか。
もともとは柔軟な思考と考え続けることの必要性を訴えるために叫ばれたこれらの言葉も、あまりに広く言われるようになり、もはや「常識を疑う」ことについて、思考停止で受け止めてはいないでしょうか。
確かな実践に定評のある土居先生は、「常識」を「適切に」疑うことの重要性を訴えます。
本書では、適切な疑い方で「常識」を乗り越えていくために、「常識」の性質をきちんと定義し、「常識」を疑うとはどのようなことかを一から見直しています。
本書では「常識」を「明文化されている、されていないに関わらず、多くの教師が『これはそういうものだ』『これはこうやるものだ』と捉えている説」と定義します。
そのうえで、「手法常識」や「概念常識」といった種類、明文化されている「常識」、されていない「常識」などと分析していき、疑うべき「常識」をあぶり出しています。
この「常識」のメリット・デメリット、いくつ説明できますか?
――「常識」にもよさがある
「常識」を疑うときの大前提は「常識=悪」ではないということです。
「常識」が「常識」となった背景には大きな長所があるはずなのです。
土居先生は、「常識」を疑い、乗り越えるときにはよさにも必ず目を向けるべきだと主張します。
「常識」の一般的なよさとして、①一定の効果がある、②持続可能であることを挙げ、「常識」を冷静に見ることをすすめます。
一方で、このよさと表裏一体をなす危険性として、①一定の成果しか出ない、②教師の思考停止を招くことを挙げています。
よさと危険性、どちらにも目を向けた上で、「常識」の乗り越え方を考えるのです。
内容説明
「常識」を疑うことは実践構想の根幹である。教育現場には「常識」が無数に存在する。「常識」には「手法常識」と「概念常識」がある。「常識」にはよさがある。「常識」にはよさと表裏一体の危険性がある。適切に「常識」を乗り越えれば子どもが育つ。
目次
第1章 「常識」を疑え(教育界に存在する無数の「常識」;「常識」の種類―手法常識と概念常識;「常識」はどのように発生し、どこに存在するのか ほか)
第2章 「常識」を分析し、改善せよ(実践を改善することと、研究をすること;「常識」の問題点を整理し、改善の方向性を定める;「常識」のよさは生かしつつ、問題点を克服していく ほか)
第3章 国語授業の「常識」を乗り越えろ―疑い、改善し、実践する(国語科指導と「常識」―国語科には「常識」が溢れている;常識1 教えたいことを直接問う→教えたいことを間接的に問う(概念)
常識2 初発の感想を書かせる→初読では「あらすじ」を書かせる(読むこと) ほか)
著者等紹介
土居正博[ドイマサヒロ]
神奈川県・川崎市立小学校教諭。1988年生まれ。創価大学大学院教職研究科教職専攻修了後、現職。東京書籍小学校国語教科書編集委員。全国国語授業研究会監事。国語教育探究の会会員。教育サークル「KYOSO’s」代表。教員サークル「深澤道場」所属。2015年「わたしの教育記録」(日本児童教育振興財団主催)にて「新採・新人賞」、2016年「わたしの教育記録」にて「特別賞」、2018年「読売教育賞」、2020年「国語科学習デザイン学会優秀論文賞」受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かるー
家主
かるー
松村 英治
川越友貴