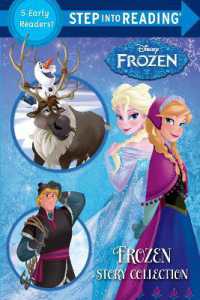内容説明
中学校・高校では、どんな学級経営が望ましいのか、生徒の幸せのために教師は何をすべきか『学び合い』から考える、新しい学級経営の本!
目次
1 なぜ、教科指導を通した学級経営が必要か?(学級経営に週何時間必要ですか?;教科学習では「ふり」ができない ほか)
2 『学び合い』のセオリー(『学び合い』のセオリー;分かれば分かるほど分からない子を教えられなくなる ほか)
3 学級崩壊したらどうすべきか(力で押さえ込めば込むほどイジメが起きる;学級崩壊の原因を考える ほか)
4 成功する学級の目標づくり(理解と納得の違いを知る;自分が所属し続けたいと思える集団をつくる ほか)
5 これからの社会での幸せな人生(教師の本当の仕事とは;この先の社会を生きていくために考えるべきこと ほか)
著者等紹介
西川純[ニシカワジュン]
1959年、東京生まれ。1982年、筑波大学第二学群生物学類生物物理学専攻を卒業。1984年、筑波大学教育修士修了(教育学修士)。1985年、東京都高校教員。現在、上越教育大学教職大学院教授。2003年、博士(学校教育)(生物、地学における巨視的時間概念に関して)。科学教育研究奨励賞(日本科学教育学会)、教育研究表彰(財団法人教育研究連合会)、理科教育研究奨励賞(日本理科教育学会)、理科教育学会賞(日本理科教育学会)受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
motoryou
2
あらためて覚悟をもって再読。わたしが〈学び合い』に初めて出会ったのは、ある新聞記事。「え?こんな授業ってあり得るの?これでうまくいくの?」と感じたのを思い出す。自分でいろいろと授業その他に課題を感じてた時期だったので、直接確かめたくて新潟に向かったのだった。分からないこと、なぜ?と思うことをしつこく西川先生に尋ね、分かるんだけどわからない…、そんなもやもやを抱えていた。大事にしてきたものを捨てたくない、そんな時思いもあったとおもう、今にすれば。本を読み漁り、実際にやってみて、その繰り返し。今なら分かる。2022/08/17
shin1
0
論理的で根拠も示されていることが多く納得できるものが多かった。理解しきれるように何回か読み込みたい。2022/09/19
motoryou
0
『学び合い』の考え方を再度おさらいするような感覚で読んだ。どんな教科の授業であれ、または行事その他であれ、一つ一つの活動に違いはあっても目的は同じ。同じだから、その結果が「学級経営」にもなっていく。学級経営のその先は、子どもたちの人生につながっていく。自分もよいし、みんなもよい、その折り合いをつけて共に幸せになるという経験を教室、学校の生活の中で積んでいければいいんだよね。何のために学ぶのか、もまさにそこだなぁ。私にとって立ち戻りたいところを確認する、そんな本。『学び合い』の手引き書のコンパクト版みたい。2022/05/31
-

- 電子書籍
- 魔尊転生【タテヨミ】第40話 picc…
-
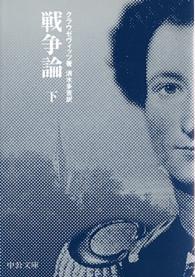
- 和書
- 戦争論 〈下〉 中公文庫


![るろうに剣心 最終章 The Final 豪華版[初回生産限定Blu-ray] Blu-ray Disc](../images/goods/ar/web/vimgdata/4943566/4943566312926.jpg)