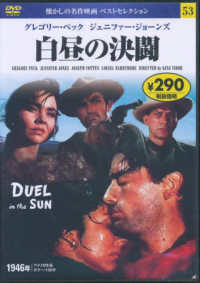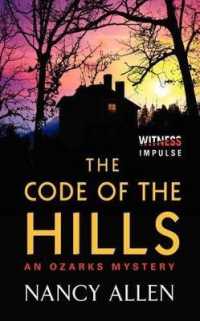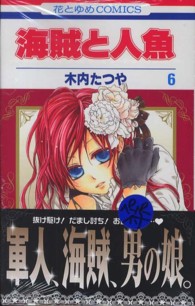内容説明
知識の構造化による豊かな見取りと質の高い授業の実現。具体的な学習活動に応じた評価規準の設定方法を徹底解説。
目次
序章 学習評価の改善過程を概観する
第1章 資質・能力を明確にする知識の構造化
第2章 学習評価の意義と役割
第3章 授業における見取りと評価
第4章 学習指導の計画と評価規準
第5章 評価規準の設定方法の明確化
第6章 知識の構造化による評価規準と子供の学び
第7章 観点別評価の総括
第8章 知識の構造化とカリキュラム・マネジメント
終章 知識はさらに駆動する
著者等紹介
田村学[タムラマナブ]
國學院大學人間開発学部初等教育学科教授(文部科学省視学委員)。昭和37年新潟県生まれ。新潟大学教育学部卒業後、昭和61年4月より新潟県公立小学校教諭、新潟県上越市立大手町小学校教諭、上越教育大学附属小学校教諭、新潟県柏崎市教育委員会指導主事を経て、文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官・国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官。文部科学省初等中等教育局視学官として学習指導要領作成に携わる。平成29年4月より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
み
14
ずっと読み進めていたが、ひとまず読了。評価の概念がかなり分かりやすい。「知識・技能」は、何ができるか、何を知っているかなのでかなり分かりやすいが、「思考・判断・表現」は、思考ツールを使って育成していことだとか「主体的に学習に取り組む態度」は、振り返りを書くことで省察できる、とかはたしかに、と唸った。聴き手の傾聴や話し合い活動のより良い様子の具体例が書かれていて、私が普段大切にしている人の話の聞き方の「はさみ」は…反応 さ…最後まで み…みて頷いて は、まんまそれだったので指導が間違ってないと自信になった。2022/01/27
家主
4
42C 大学で聞いたことがあるような、難しい言葉がたくさん出てきて、読み進められなかった。図解も、一見わかりやすそうだが全然ピンと来ない。ただ、主体的に学習に取り組む態度についての説明は、よくわかった。2021/08/02
松村 英治
2
帯の通り、評価規準の設定方法や表現様式のモデルは本当によく分かった。全教科等で活用できる。しかしその評価規準で「記録に残す評価」をクラス全員に実際にできるかは本書では分からなかったし、難しいと思う事例もあった。さらなる実践研究が必要。2021/05/03
sakai
1
教員にとって必要で重要なことが書かれています。しかし、一度読んで理解して実行することはできません。何度か読み返したり、関連本を読んだりしなければいけません。教員にそんな時間があるのか。行政も縦割りですが、この本のような専門書も縦割りです。教科等横断的という言葉がありますが、教育活動を横断的に捉えた本が必要です。評価と部活動と働き方改革を関連させて書かれた本などがあると、教員にとって有益だと思います。2022/01/09
読書家ぴろきち
0
評価規準については子どもの具体的な姿を思い浮かべながら書けるようにしたい。図解されている部分が今後指導案を書くときに参考にできそう。2022/08/23
-
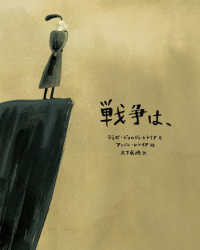
- 和書
- 戦争は、