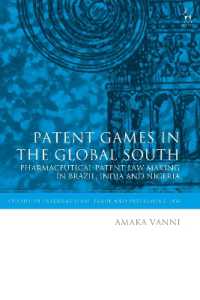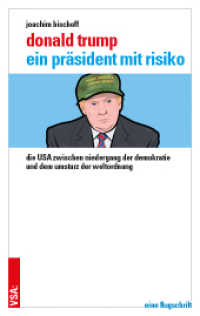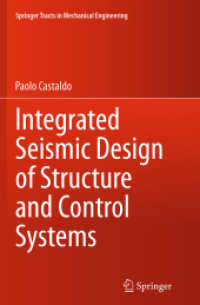出版社内容情報
国立大学附属ではわずか2校の先鋭的な小中一貫校である義務教育学校。その最先端のプロジェクト型学習の取り組みに迫る!!諸外国の研究者からも注目される、複数年横断のプロジェクト型学習の取り組み。
自主的、協働的に問題解決に取り組む、児童・生徒の姿勢はどのように醸成されてきたのか。
9カ年の学びを見取る義務教育学校だから見えてきた、これからの小・中学校のあり方を拓くプロジェクト型学習の実践記録。
福井大学教育学部附属義務教育学校研究会[フクイダイガクキョウイクガクブフゾクギムキョウイクガッコウけんきゅうかい]
著・文・その他
秋田 喜代美[アキタ キヨミ]
著・文・その他
内容説明
小中一貫の義務教育学校での総合的な学習の時間を中心としたプロジェクト型学習の実践記録。
目次
第1章 学年プロジェクト「探究のストーリー」―7~9年生
第2章 子どもたちが語る、培われる「資質・能力」―8・9年生
第3章 学年プロジェクトのカリキュラムデザイン
第4章 社会創生プロジェクトのデザイン―3年生
第5章 教科学習におけるプロジェクト型学習のカリキュラム
第6章 義務教育学校開設への道のり
第7章 教育学の側面からの学年プロジェクトの分析
終章 義務教育学校の使命
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
UP
1
小中9年間のマネジメントされたカリキュラムの中で位置づけられたプロジェクト型探究の記録。といっても実践のスケールは3年間。1回の授業、1学期間ではない。3年間継続して1テーマを学年全生徒が探究するという一見不可能そうに見える学び。教科をこえた教師間の協働はもちろん、教科学習にも好影響。原点にあるのは、どんな生徒を育てるのか、教育ビジョンが共有されていること。ビジョンの共有・教員の協働、これができるか。本書はもう少しつまづき・ためらいも見たかった。120人全員なの?というのを教員目線ではないもので読みたい。2019/03/17
空を歩く人
1
教科横断的なプロジェクト学習の進め方、それも組織的なアプローチにまで触れられている中学校としてはとても先進的な取組。 学級に閉じず、中学校の組織としての強さをここまでしっかり利用している取組は他に聞いたことが無かった。 ただ、最後のアフトプットが総合学習ぽくなかったのが少し残念。2019/01/30
mi78621
0
3年間を貫く学P、長期的ビジョンの基、まさに子どもたちの主体的な学びを保障する価値ある学習であると思う。本書からはリーダーとなる子どもたちの動向についてはよく伝わってきたが、先頭集団ではない子どもたちは一体どんな様子だったのだろうと関心をもつ。また、小学校にあたる前期課程の様子もさらに詳しく知りたいところ。2019/04/17