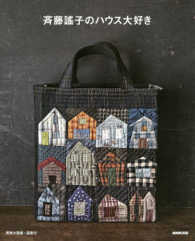出版社内容情報
イメージや経験談からではなく、理論的に学ぶ。全く新しい学級経営のための「教科書」刊行!イメージや経験談からではなく、理論的に学ぶ
全く新しい学級経営のための「教科書」!
はじめに 001
第1部 学級経営の三領域
第1章 学級経営の基礎と三領域 014
1 学級経営とは何か? 015
2 学級経営の二つの潮流 016
3 学級経営の三領域 019
Column01 学級経営のエビデンスとは? 033
第2章 〈学級のあたたかさを創る〉必然的領域 035
1 必然的領域では何を指導するか? 036
2 学級のあたたかさとは? 043
3 「排除の論理」から「包摂の論理」へ 045
4 多様性を尊重する二十一世紀型学級経営へ 047
Column02 個を大切にする学級経営:ある小学校教師のライフヒストリー 053
第3章 〈できることを増やす〉計画的領域 056
1 計画的に指導する「きまりごと」とは? 057
2 計画的領域の指導 067
3 計画的領域における指導の三つのコツ 075
Column03 「黄金の三日間」を再考する 084
第4章 〈ともに学級を創る〉偶発的領域 087
1 なぜ、学級経営に偶発的領域が必要か? 088
2 ホスピタリティと一体感 090
3 自治的領域:文化を創造するコミュニティ 092
4 自律的領域:非認知的能力の育成 100
Column04 先生の思いを超える学級:ある中学校教師のライフヒストリー 109
第2部 学級活動を通じた学級経営の充実
第5章 学級経営の指導スタイル 114
1 学級経営の指導スタイル 115
2 「インクルージョン」と「インターベンション」 118
3 「トラウマ刺激」にみる「内省」の必要性 122
4 「インストラクション」と「コーチング」 124
5 「ファシリテーション」と「コーディネーション」 126
Column05 話合い活動のファシリテーションを充実させるために 132
第6章 「自律」をめざす指導 135
1 「自律的」な活動や行動のある学級とは? 136
2 「意志力」「やり抜く力」という視点 137
3 生徒指導が「しつけ」になりがちな理由 138
4 「子どもの変容」を生む指導の難しさとやりがい 140
5 「自律」に向かう指導とは? 143
Column06 「ぶつからない指導」だけでいいのか? 152
第7章 「自治」をめざす指導 154
1 学級は「もろ刃の剣」 155
2 自治的活動としての「協働的な文化創造」 158
3 教師のキャラクターとストーリーテリング 162
4 協働的な文化創造のための三つの軸 165
5 自治的活動を促進するには? 180
Column07 組体操問題とは? 無内省性・無反省性の問題 195
第8章 組織的な取り組みによる学級経営のエンパワメント 198
1 学級活動Plus 200
2 トラブルや保護者への対応 208
Column08 子どものトラブルに介入する? しない? 228
おわりに 232
白松 賢[シラマツサトシ]
白松賢(Shiramatsu Satoshi)愛媛大学大学院教育学研究科教授。1970年山口県生まれ。広島大学大学院教育学研究科、徳島文理大講師、愛媛大教育学部講師を経て現職。主な研究分野は学校/学級経営、特別活動、教育社会学。共著に『個性をひらく特別活動』『入門 子ども社会学』(ミネルヴァ書房)などがある。中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会 特別活動ワーキンググループ委員。
内容説明
小・中・高を貫く「学級経営の充実」の視点。イメージや経験ではなく、理論的に学ぶ学級経営。
目次
第1部 学級経営の三領域(学級経営の基礎と三領域;“学級のあたたかさを創る”必然的領域;“できることを増やす”計画的領域;“ともに学級を創る”偶発的領域)
第2部 学級活動を通じた学級経営の充実(学級経営の指導スタイル;「自律」をめざす指導;「自治」をめざす指導;組織的な取り組みによる学級経営のエンパワメント)
著者等紹介
白松賢[シラマツサトシ]
愛媛大学大学院教育学研究科教授。1970年山口県生まれ。広島大大学院教育学研究科、徳島文理大講師、愛媛大学教育学部講師を経て現職。主な研究分野は学校/学級経営、特別活動、教育社会学。中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会特別活動ワーキンググループ委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Fugin
あべし
mori
U-Tchallenge
taku