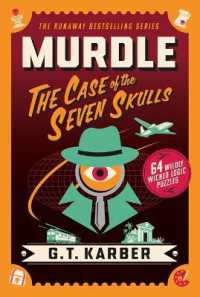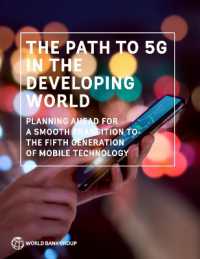内容説明
12の仕掛け、7つの授業スキル、7つのアクティブ・ワードetc.実際の授業場面をもとにわかりやすく解説!
目次
第1章 「アクティブな授業」ってどんな授業?
第2章 最初の3ヵ月で子どもが変わる
第3章 「問い」の連続がアクティブ・ラーニングをつくる
第4章 「12の仕掛け」でアクティブな授業をつくる!
第5章 こんな「授業スキル」で子どもはもっとアクティブに!
第6章 授業で大切にしたい「7つのアクティブ・ワード」
第7章 「アクティブ・ラーニング」=「問題解決授業」?
特別寄稿 アクティブ・ラーニングがめざす方向 小松信哉(国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部学力調査官兼教育課程調査官)
著者等紹介
尾崎正彦[オザキマサヒコ]
新潟県佐渡郡佐和田町(現・佐渡市)生まれ。新潟県内公立小学校勤務を経て、現在、関西大学初等部教諭。リクルート・スタディサプリ講師(小学校算数基礎講座)。全国算数授業研究会常任理事。新潟市教育委員会認定・第1期マイスター教師(算数)。学校図書「みんなと学ぶ小学校算数」教科書編集委員。第6回東京理科大学「数学・授業の達人大賞」優秀賞。第41回小学館「わたしの教育記録」特選(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
totuboy
2
いわゆる、従来言われてきた問題解決型授業の問題点を指摘し、子供たちの力を伸ばすためにどうすればいいのかを提案している。授業の進め方が「型」になることは、教師にとってはある一定のレベル以上の指導が期待できる一方で、子供にとっては必然性がなく、主体的に取り組めなくなることが問題。ただし、問題解決学習でも、その活動の意味がしっかりと分かっていれば十分に対応できるところもある。2016/07/28
Mr.Y
0
校内研修、外部の算数の研究会に参加することをきっかけに再読。子どもの問いを生み出す問題解決の授業への道筋が丁寧に示されている。問題解決型の授業と問題解決の授業が目指す方向性は同じであるが、問題解決型の授業は子どもを受身にしていく授業であることも例示されており、校内に研修でも活用できる。次年度は算数の授業に力を入れたくなった。2017/02/25
jotadanobu
0
アクティブラーニングへの12の仕掛け。早速ノートに視写し、それを眺めながら教材研究をしていると、どんどんアイデアが湧いてきた。やはり闇雲ではなく、こうした視点を得てやっていくことはとても大切だと感じた。 誤字が多いのが少し気になった。2016/08/21
Horizon09133
0
中学校でも使える至言が多数。 今年の少ない授業時間数の中で、どんなアクティブな授業を展開できるか。うまくやれば、一気に内容が進むこともあるだろうし、停滞することもあるだろう。どーんと構えてやっていかなければいけないと思う。田中博史先生の本と合わせて読むと、子どもの意見の取り上げ方が変わってくるなと感じた。2020/05/25
エース
0
子どもの価値ある呟きを価値づけることを意識して取り組んできた。しかし、何でもかんでも問い返していたということがある。やはり本時の狙いに迫る、数学的な考え方を問い返すことを意識したい。また『ここは共有しないといけない』場面というものがある、しっかり逃さないように共有化したい。そうすることで授業にリズムが生まれるように思う。尾崎先生が授業づくりで意識していることがだいぶ見えてきた、自身の授業づくりから取り入れたい。最初の三ヶ月が勝負である。2020/02/22
-
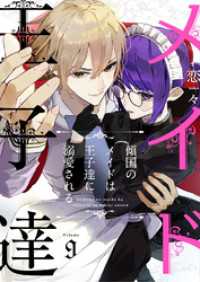
- 電子書籍
- 傾国のメイドは王子達に溺愛される 9話…