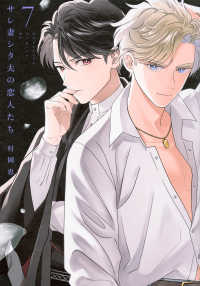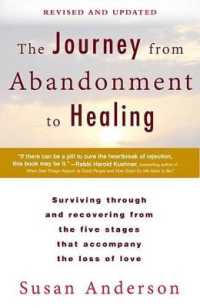内容説明
子どもの思考のスタートラインを揃えると…既習が明確になる!自然と知識が積み上がる!!全員がめあてを達成できる!!!子どもの学力差に左右されない問題解決学習を!
目次
第1章 子どもの思考のスタートラインを揃えるビルドアップ型算数授業(子どもの「思考のスタートライン」を揃える!(4年「わり算の筆算」)
全員で解決方法の水準を高めていくことで、わり算の筆算を「創る」 ほか)
第2章 子どもが動く教材をつくる(ゲーム感覚で算数を楽しむ(5年「奇数と偶数」)
教材づくりの大切さ ほか)
第3章 発想する力を育てる(「創る」ことで「自分のもの」にさせる;子どもの「発想」を問う(6年「分数のかけ算」) ほか)
第4章 概念を構築する授業(子どもと概念を創る(2年「三角形と四角形」)
算数を再発明させる(1年「長さ比べ」) ほか)
著者等紹介
大野桂[オオノケイ]
1976年東京都生まれ。東京学芸大学卒業。私立高等学校、東京都公立中学校、東京学芸大学附属世田谷小学校の教諭を経て、2010年より筑波大学附属小学校教諭。専門は算数教育。全国算数授業研究会常任理事、日本数学教育学会幹事、ベーシック研究会常任理事。全国各地の小学校で授業や講演。JICA専門委員としてウガンダでも授業や講演などを行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
後藤か
2
ビルドアップ算数とはなんぞや!?ってことで読破。誰もが算数に取り組めるように思考のスタートラインを揃えるという考えには賛同。尻すぼみの授業ではなく最後まで生き生きとしした授業がやりたいから。本の中で何個か実践を紹介しているが、これば難しいものが多い。それもそのはず。筑波大学附属(全国トップ偏差値75)だもんなぁ。全員を揃えるという概念は賛同だけど、公立校だと何年も前に遡らなきゃになっちゃう。偶数奇数のマグネット当てや掛け算の秘密などなど、アイディアは参考になったので活かしていきたい。教材研究が大切2025/05/14
Susumu Nakakoshi
0
全員を授業の舞台にあげる、理想だけどもなかなかできません。大野先生の本にヒントがたくさん隠されていました。ビルドアップをどう仕組むかを私も考えていきたいです。2017/02/19
読書家ぴろきち
0
教材研究がすごい。 特に導入部にこだわってやっている。 これらの実践を真似することはできるが、この研究を真似することは到底自分には無理だと思った。 スタートラインを揃え、無理なく築き上げていく授業。速さの導入とか、三角形の導入、長さくらべの導入はやってみたくなった。2020/02/20