内容説明
山東京伝・京山、曲亭馬琴、岡田玉山、鈴木芙蓉ら江戸・大坂の人気作家・絵師らを巻き込み、40年もの歳月をかけてできあがった本、それが『北越雪譜』である。越後塩沢からの持ち込み企画が、江戸で全7巻の本になるまでの一部始終を再現する!
目次
ある「雪の本」をめぐる歴史
第1部 雪の本への途(江戸の書物と辺境・異界・雪国;越後と牧之、文化の大衆化の中で)
第2部 雪の本とそれぞれの思惑(京伝・玉山・芙蓉、そして牧之;馬琴・京山、そして牧之)
第3部 『北越雪譜』を編む(馬琴・京山の出版ノウハウ;本をつくる―京山・牧之の協働;板本『北越雪譜』を解く)
雪国を江戸で
著者等紹介
森山武[モリヤマタケシ]
1960年、新潟県生まれ。法政大学BA(哲学)、シドニー工科大学GradDip、マードック大学MAおよびPhD(学術博士History & Asian Studies)。1991年より豪在住。現在、マードック大学グローバル・スタディーズ学部教授(Senior Lecturer)。学習院大学客員研究員(2016年)、成蹊大学外国人特別教員(2018年)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
75
江戸時代にあって雪国を扱う本など珍しいに違いない。唯一かどうかは知らなかったが、牧之の魚沼には及ぶべくもないが、富山も嘗ては雪国だった。38豪雪当時の光景は今も脳裏に刻まれている。あの惨状が毎年の光景とは考えたくもない。 雪景色は、雪を知らないか滅多に降らない地方と雪国とでは受け止め方はまるで違う。雪景色を単純に美しいとか楽しみと思えるのは、雪を知らないか、大人の労苦を知らない子供だろう。2020/10/03
天の川
57
研究書。保存された多くの書簡から浮き彫りにされていく江戸の出版文化。地域で一目置かれる豪農の文化人・鈴木牧之の、雪国の生活を知らしめたい情熱は地元で自慢し全国に自分の名を広めたい欲でもあった。江戸の文化人の地方に対する優越感、江戸・大阪と越後を繋いだ俳人ネットワーク。版元に請われての出版と自費出版とは現代も同じか。京伝・馬琴・京山それぞれの考える売ろうとする本の違いも面白い。京山の細かい見積書(図版の版木彫が一番高い!当然、図が細かくなるほど一枚当たりのお値段も上がる)、自身の校正・加筆料も牧之に請求。→2025/01/27
gorgeanalogue
5
越後の鈴木牧之『北越雪譜』をめぐる近世出版文化を活写する。書翰の緻密な読みをもとにしており、具体的で些細なやり取りが彷彿として面白かった。牧之と山東京伝・京山、曲亭馬琴らの一流の文人とのやり取りの機微は現在の出版界ともそう変わらない、というよりこの頃に原型ができたんだろう。2020/08/02
つまみ食い
3
鈴木牧之によるものか、山東京山の代作か議論のある『北越雪譜』。この本について地方における富農の登場と文化資本の蓄積、地方と中央の知識人をつなぐ全国的ネットワークの発展、出版市場の成熟といったその出版の前提となる事柄についても平易に解説しながら検証している。 国文学の研究書をあまり読んだことがなかったが、そんな門外漢にもわかりやすく面白い良書だった。滝沢馬琴と牧之、京山の三角関係なども描かれています。2020/09/08
志村真幸
1
本書は、『北越雪譜』の成り立ちについて、残された書簡と江戸の出版文化の側面から追求した内容だ。 『北越雪譜』は、鈴木牧之が出版を志してから、実現まで40年かかったことが知られているが、その間の経緯がていねいに解きほぐされている。 資料の分析によって、この一連の流れがはっきりと示されている。 地方の知識人が江戸で「郷土ネタ」を本にするということを通して、江戸の出版文化がよく見えてくる。 そして、実際に『北越雪譜』の文章を誰が書いたのかという点も、きわめて説得的に解き明かされていた。 2023/01/04
-
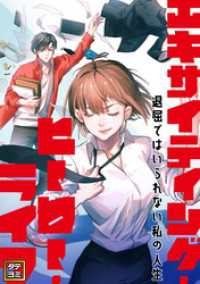
- 電子書籍
- エキサイティング・ヒーロー・ライフ~退…
-

- 電子書籍
- 強殖装甲ガイバー【分冊版】 37 角川…
-
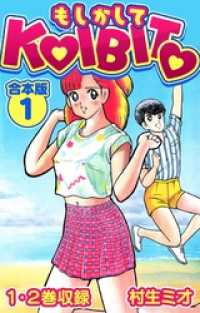
- 電子書籍
- もしかしてKOIBITO 合本版 1 …
-

- 洋書電子書籍
- ウォーフ『言語・思考・現実』(第2版)…
-
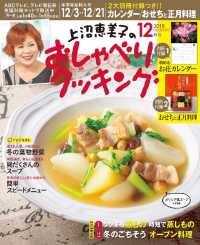
- 電子書籍
- 上沼恵美子のおしゃべりクッキング201…




