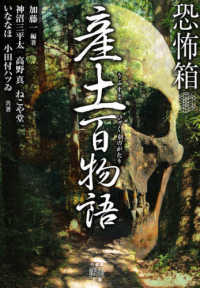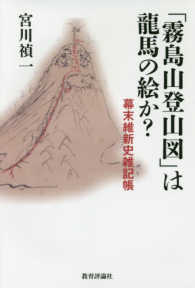内容説明
たのしい天文学の世界へのやさしくておもしろい道案内。
目次
宇宙のおしゃべり
宇宙時代
星空の旅
極と赤道
星空をかざる動物の輪(黄道12宮)
太陽の家族
コペルニクス、ケプラー、ニュートン
惑星たち
水星
金星
地球の衛星―月
火星に生物はいるのか
彗星と隕石
最も近い恒星―太陽〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なかち
1
時計、羅針盤、暦には天文学が欠かせない。一等星は六等星よりも百倍明るい。望遠鏡を天文学に使い出したのはガリレオ。昔は望遠鏡を見ながら星をスケッチしていた、今は写真。光を放射する物体はどれも「スペクトル」で温度と化学成分がわかる。天文学には物理学の知識を応用する。戦争中、戦闘機を見つけるための電波探知局は戦争後、宇宙の電波を解析する天文学者の観測所になった。ロケットは作用反作用の法則で飛ぶ。星座で一番明るいのがα、次がβ。星の位置は赤道座標で表記。十二星座は太陽が通り道。火星に運河があると思われていた。2011/07/24
Mariamaniatica
0
やさしい・・とありますが、やはり基礎知識はあった方がより良いです。それでも系統立てて良く整理されていると思います。ガリレオ、コペルニクスなどについても読んでみたくなりました。2011/08/14
-
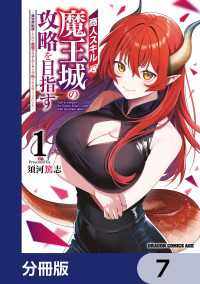
- 電子書籍
- 商人スキルで魔王城の攻略を目指す【分冊…
-
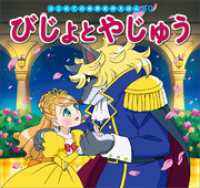
- 電子書籍
- はじめての世界名作えほん 50 びじょ…