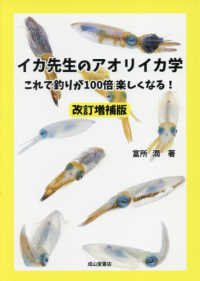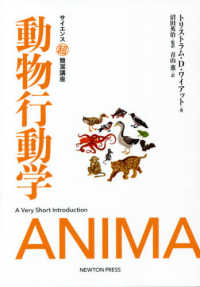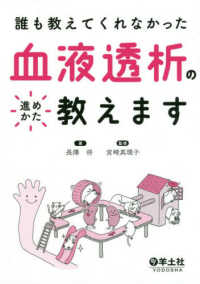感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
338
太陽プロミネンスの変調によって異常な高温と化した地球。温帯のほとんどの部分は水没している。かろうじて生活圏を持てそうなのはもはや極地のみといった限界状況が描かれる。ニューウェーヴSFと呼ばれたバラードの作品群も、半世紀を経て今やSFの古典となった。バラードが新たに拓いた地平はSFの未開拓地であっただろう。すなわち、インナー・スペースである。それと同時にここには、独特のペシミズムを内包した終末世界がある。文明も、進化も、そうしたすべてを遡行したところにある原質に迫ろうとする試みだろうか。ただし、私には⇒2017/12/25
まふ
121
太陽の異変により気温が50度以上にもなり地球高熱化・海面上昇が進み、地球の主要都市が水没し、大半の人類が死滅する。国連の調査隊員のケランズは人の住めない赤道を目指して研究をつづける…。1962年に発表された近未来予測のSF 。今日の地球の気象はその通りの世界になりつつある。ならば、どうすればよかったのか?ということは何も語っていない。語れるはずがない。すべては我々およびこれからの世代の行動にかかっているわけである…という意味で、作者のJ.G.バラード氏に感謝すべき作品だった。G555/1000。2024/07/06
ケイ
95
地球の温度が上昇し、南極の氷は解け、都市は水没している。温暖化の影響ではない。書かれたのは半世紀前。前提は、太陽の異常な活動によるものだ。かつて都市があった場所では、ビルの上の方が水面から出ている。当時はセンセーショナルなSFだったのかもしれないが、今読むと、色々な矛盾が目につく。しかし、その中で生きている人の倦怠感と自ら研究を続ける研究者の様子になぜか惹かれるものを感じ、これは絶望の物語ではないような気になる。太陽の異常に対しては、人間などなすすべもないのに。2015/12/14
扉のこちら側
79
2016年286冊め。【167/G1000】気候変動により主要都市のほとんどが水に沈んだ近未来。60年代に書かれたということで、科学的には矛盾もあるが、昨今でいう温暖化によるものではなく物理学上の原因によるものらしい。熱帯気候になれば植物や動物の生態系が変わるのはそうだが、爬虫類の描写を読むまで現実にもこういうことが起こりうるとまで想像していなかった。潜水シーンは美しい。2016/04/30
Vakira
58
バラードさん狂風に引続き、今度は温暖化による溺れた世界。ロンドンでは気温53℃となる。しかし、この状況となった原因は、温室効果ガス排出量過多の所為ではない。太陽の異常爆発。太陽風は地球のバンアレン帯を一部吹き飛ばし、太陽光は直接地球に届くことから気温の上昇となったのだ。北極、南極の氷は解け、海抜は上昇、主要都市は海底に沈む。また、太陽の放射能は動植物の遺伝子にも影響、雑草は巨大シダ類となりジャングル化。トカゲはイグアナ大となり時に人間を襲うことも。ワニは溺れた都市を闊歩し、人類は高温を避け、北極、南極へ。2024/12/25