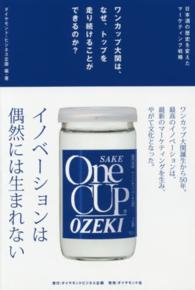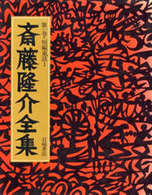内容説明
マーティン家に送られてきた家政用ロボット、アンドリューには、いかなる偶然からか、本来ないはずの芸術的才能が備わっていた。一個の家電ではなく一人の友として遇されるうちに、彼はロボットと人との違いを探究するようになる。法的自由を、衣服を、そして人間そっくりのボディを求めた彼が最後にたどりついた結論とは?ロボットSFの傑作「バイセンテニアル・マン」長編版。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鐵太郎
22
中編「バイセンテニアル・マン」をシルヴァーバーグと共作で長編に仕立てたもの。人間になりたかったロボットの生涯。「エン・ディー・アール・・・ そんなのだめよ。絶対にだめ。アンドリューって呼んだらどうかしら」「アンドリュー?」「nがひとつあるでしょ? それにdがひとつかな? ・・・ そうよ、それにrがひとつ、それにまちがいないわ。N-D-R。アンドリュー」 ──アメリカが抱える様々な問題を背景に、アシモフとシルヴァーバーグが書き上げた珠玉の逸品です。2005/04/16
よむヨム@book
21
★★★★☆ 星4つ 映画「アンドリューNDR114」の原作本。 映画版が好きで読んでみた。 映画版は映像用に脚色され、ロビン・ウィリアムズの演技もよかった。 この本の冒頭からシュールな話で始まり、おもわずニヤリとしてしまった。 本も映画もテーマは変わらず、人間とロボットの違い、人間とは、権利や自由などについて考えさせられた。 ただ、何十年後、何百年後かわからないが、未来の子孫たちはこのテーマを真剣に考えざるおえないだろう。2022/02/17
Yoko
16
近未来、人間のパートナーとして機能的には究極のところまで進化を遂げるロボット。人間に使役されることを目的として作られながらも、それが芸術的才能のみならず人間のように移ろう心を持っていたとしたら‥‥‥。そんなロボット、アンドリューの視点や生き方(あえてそう言う)を通して人の人たる所以を考えることを突きつけられる。私にとっては苦手なSFではあるがヒューマンドラマ的な色合いが濃く心温まる作品で一気に読みました。2015/08/29
k16
12
バイセンテニアル・マン読もうと探したが見つけられず長編の本作を。 エラー品である家政用ロボットが人間になるための苦悩と挑戦物語。 人間とロボットは何が違うのか。結末は切ない。 映像作品未見。2020/08/26
roughfractus02
11
1976年発表の短編「バイセンテニアル・マン」をシルヴァーバーグとの共作で1993年に長編化された本書は1999年に映画化された。対照するとその背景にある20年近くのAI開発の方向が長編化に反映しているように思える。自らの身体に死をセットすることで人間と同等であることを社会に承認させた短編の背景には、AIに人間を超える能力を持たせるという当時の理念が仄見える。が、長編では人間とAI搭載ロボットの境界はどこにあるのかという人間の能力を探究するAI開発方向性が垣間見える。短編での感動は、長編では不安に変わる。2023/08/06