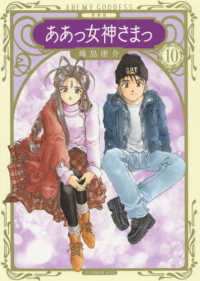出版社内容情報
みさき書房の編集者として新潮社を訪ねた《私》は新潮文庫の復刻を手に取り、巻末の刊行案内に「ピエルロチ」の名を見つけた。たちまち連想が連想を呼ぶ。卒論のテーマだった芥川と菊池寛、芥川の「舞踏会」を評する江藤淳と三島由紀夫……本から本へ、《私》の探求はとどまるところを知らない。太宰が愛用した辞書は何だったのかと遠方にも足を延ばす。そのゆくたてに耳を傾けてくれる噺家。そう、やはり「円紫さんのおかげで、本の旅が続けられる」のだ……。《円紫さんと私》シリーズ最新刊、文庫化。
内容説明
大人になった“私”は、謎との出逢いを増やしてゆく。謎が自らの存在を声高に叫びはしなくても、冴えた感性は秘めやかな真実を見つけ出し、日々の営みに彩りを添えるのだ。編集者として仕事の場で、家庭人としての日常において、時に形のない謎を捉え、本をめぐる様々な想いを糧に生きる“私”。今日も本を読むことができた、円紫さんのおかげで本の旅が続けられる、と喜びながら
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
189
文学探究の営為が延々と続き、もはやミステリと呼べるのか、とさえ思った。読み終わってみると「確かにミステリだ」と感じた。人が死ぬわけではない。事件すら起こらない。しかしそこにもミステリの成立する余地はあるし、また読者を感心させる要素も盛り込めるのだと思った。「私」と円紫さんのあり方も時代的に変わったけれど、「日常の謎」は立派に生きていると思った。2017/10/27
紅はこべ
173
これは元々文庫版は東京創元社から出す予定だったのかな。ハードカヴァーは借りて読んだけど、当然これは買いました。文庫オリジナル短編の少年は円紫師匠?本シリーズの中で『六の宮の姫君』に続く、本に特化した連作。引用部分が最も多い。文芸雑誌を出す文藝春秋と週刊誌を出す会社は、人格ならぬ社格が違うのかな。佐藤亜紀さんは、文芸の文藝春秋にも厳しいけど。作中に引用された芥川比呂志の言葉、似たようなこと、姫川亜弓さんが言っていたような。正ちゃん、生徒から本を没収したら、ちゃんと返してね。2018/03/03
佐々陽太朗(K.Tsubota)
140
主人公が社会人になった時点で完結したと勘違いしていたが第六作が出た。本作では表紙の画を見ても主人公は落ち着いた人妻風情である。結婚して、今も出版社に勤めており、中学生の息子がいるのだ。なるほど、たいへん喜ばしいことである。円紫さんはいつもながらの博覧強記ぶりを発揮します。円紫さんと私のやりとりは文系人間にはたまらないところ。「女生徒」にでてくる大学時代の同級生「正ちゃん」とのやりとりもそうなのだが、文学をめぐっての会話ににじみ出る知性が本シリーズの醍醐味である。分かる奴にしか分からないってことですね。2019/03/11
mocha
132
40代になった「私」と書物の探索行。登場する作品を知らないとかなりとっつきにくい。なので芥川『舞踏会』太宰『女学生』を読んで臨む。引っかかりを覚えた箇所が謎として取り上げられ、ちゃんと答えを示してもらえたので、とても入り込んで読むことができた。解説で米澤穂信氏は“翻案”という言葉を使っているけれど、もし太宰治が現代の作家だったら、ネットや週刊誌で吊るし上げられただろう。「白い朝」で円紫さんの子ども時代に会えたのは嬉しいオマケ。やはり双葉より芳し。2017/11/14
gonta19
124
2017/10/12 Amazonより届く。 2017/12/29〜12/31 2017年の最後は何を読もうと考えたとき、これしかないと、予定を変更して読む。17年ぶりのシリーズ復活。芥川と太宰の作品を題材に、中堅編集者で中学生の子持ちになった<私>が、謎を追いかける。当然ながら円紫さんも登場。懐かしさに感動ものである。米澤穂信さんの解説も素晴らしい。 これで小説は読み納め。来年はどんな本に出会えるだろうか。2017/12/31
-
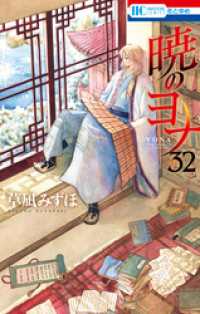
- 電子書籍
- 暁のヨナ 32巻 花とゆめコミックス