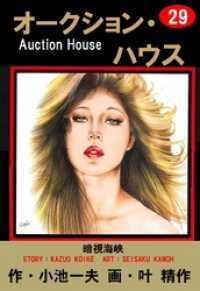出版社内容情報
16人の在野研究者たちに学ぶ、「やりたいこと」をやりながらも、しぶとく生き延びるための<あがき>方。その心得、40。
「やりたいこと」をやって生きる。
その<あがき〈struggle〉>方は、今も昔も、無数にある。
先人に学び、選択肢を増やすため、16人の<在野研究者>の「生」を、彼らの遺した文献や、伝記的事実から読み解く。
大学や組織などに所属せずとも、しぶとく「生き延びる」ための<あがき>方の心得、40。
内容説明
16人の在野研究者たちの「生」を、彼らの遺した文献から読み解き、アウトサイドで学問するための方法を探し出す。大学や会社や組織の外でも、しぶとく「生き延びる」ための、“あがき”方の心得、40選。
目次
第1章 働きながら学問する
第2章 寄生しながら学問する
第3章 女性と研究
第4章 自前メディアを立ち上げる
第5章 政治と学問と
第6章 教育を拡げる
第7章 何処であっても、何があっても
著者等紹介
荒木優太[アラキユウタ]
1987年東京生まれ。在野研究者(専門は有島武郎)。明治大学文学部文学科日本文学専攻博士前期課程修了。En‐Soph、パブー、マガシン航など、Web媒体を中心に、日本近代文学関連の批評・研究を発表している。2015年、「反偶然の共生空間―愛と正義のジョン・ロールズ」が第59回群像新人評論賞優秀作となる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
45
大学や研究機関に属していない在野の研究者への心得。日本の16人の在野研究者を取り上げ、彼らの生涯と教訓を語る。勉強時間と生活のための時間の両立は永遠の問題のようだ。変人?が多いせいもあるがなかなか面白い読み物だ。ただちょっと物足りないか。40の心得があるが、11『周囲に頭がおかしいと思わせる』…… ネットで連載されていたものを書籍化したようだ。三浦つとむ、谷川健一、相沢忠洋、野村隈畔、原田大六、高群逸枝、吉野裕子、大槻憲二、森銑三、平岩米吉、赤松啓介、小阪修平、三沢勝衛、小室直樹、南方熊楠、橋本梧郎2016/08/18
T2y@
35
『本当に学ぶ事が出来る人は、大学の外にいる人々である。』 施設・設備・学閥不要で、現場学習が有効な民俗学などが、在野研究向けジャンルの様だ。 道標たる四十からなる『心得』も描かれているが、南方熊楠ほか取り上げられた16名の破天荒な評伝を読む限り、この道を躊躇するのが妥当であろう。 が、そこを乗り越えた処に生き場所があるのだろうな。2016/07/04
アナクマ
30
在野研究。光る言葉だ。「本棚遊びで英語とドイツ語を習得し…7歳で失明…初等教育を受けず…視力回復…18才で天涯孤独…沖仲仕として働きながら…39才で論文を…」「もちろんエリック・ホッファーのことである」。というわけで、古今の在野研究者集成本。 ◉大学に対するウラミ成分が多めな気がするけど(もともと、アカデミズムは大学に飼い慣らされない!)「カウンターではなくオルタナティブとして」提案される〈外側の〉研究/研究者たち。「私たちのツマラナイ日常をオモシロで満たすための希望の道筋である」。良い。2024/10/12
シッダ@涅槃
28
エリック・ホッファーについて平易そうな本が出たな、と思って図書館にリクエスト。内容的には裏切られた結果になったが良い意味での裏切り。ハンナ・アーレントによるLabor,Work and Actionという腑分けを紹介されただけでも(Laborに意味を見出すことは半ば諦めた身には)エンカレッジングなものを感じた。細かい発見はいくつもあるが(『マンガ夜話』の大月隆寛さんがこんなに凄かったなんて!など)ホッファーが在野のアフォリストではなく「研究者」だったことが一番の驚きかもしれない。2017/01/29
yutaro sata
24
大学という公的ルートでの学びがかなわない、あるいは向かない人が、それでも在野でどのように学問をしていくか、先人に倣ってみようという本。学問と労働の時間配分、学問と相性の良い労働は何か、他の人とのネットワークの作り方などなど、参考になるポイントが多数。どの先人も、現実とネゴシエーションしながら、自分独自の学問空間を確保するための闘いを、粘り強く、一生涯かけて行っているという感じ。 後はつぶやきの方でも書いたが、学問を続けるためには体力、体力、体力。これに尽きる。あと気力もか。急がば回れで運動を継続する!2023/04/28