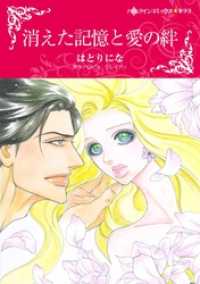内容説明
歴史は進化する。古代から近代まで、今、新しい歴史が始まる。
目次
第1章 古代(人類登場の年代はどんどんさかのぼる?―人類の出現;遺跡の発掘で変わる時代像―三内丸山遺跡 ほか)
第2章 中世(「いいくにつくろう鎌倉幕府」と覚えたけど…―鎌倉幕府の成立年;え!これは頼朝ではないの?―源頼朝の肖像画 ほか)
第3章 近世(あのいかめしい肖像画は信玄ではなかった?―武田信玄画像;合戦に武田の「騎馬隊」はいたのか?―長篠の戦い ほか)
第4章 近代(イギリスの植民地支配への抵抗―インド大反乱;日本に開国を要求したアメリカの目的は中国との貿易だった!―日米和親条約 ほか)
著者等紹介
山本博文[ヤマモトヒロフミ]
昭和32(1957)年、岡山県生まれ。東京大学文学部国史学科卒業後、同大大学院を経て、57年東京大学史料編纂所助手、平成6年助教授、13年教授。文学博士(東京大学)。『江戸お留守居役の日記』で第40回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
G-dark
22
中学校の教科書の1972年版と2006年版などを比較しながら、その30年以上もの間に、記述がどう変わったのか、何故変わったのか考察している本。古代から近代にかけての日本史について書かれており、それらの時代に外国ではどんなことが起こっていたかについても紹介されています。わたしは「2006年版ではこう書かれているのか! かつて受けた日本史のテストは間違いだったのか!」と驚いただけでなく、「1972年版にはこう書いてあったのか…」と、また違う意味での衝撃を受けました。2012/12/13
higurashi_jp
10
歴史って変わるんだなと思った2017/08/22
圭
7
1972年と2006年の歴史教科書を比較し、聖徳太子像、源頼朝像、足利尊氏像は本当は別人?士農工商はなかった?など内容的に変更された部分をいくつかピックアップして、近年の定説や有力説を紹介した本。「江戸時代、武士身分を株として販売していた」等、読み物として面白いと思います。もともと歴史や社会学は、科学的・客観的な根拠に乏しい傾向が強い分野で、根拠がかなりいい加減だったり、本当のところはよくわからない、諸説紛々ってよくある事なのですよね。検証も大事ですし、教科書だからと鵜呑みにしない姿勢も大切ですね。2013/12/28
なーちゃま
5
1972年と2006年の記述を比べながら、歴史認識が改まるにつれ改定されたことを説明している。2020年でも多くの箇所が改定されているだろう。 銀座設置は京都が初。銀遣いの西日本の銀の質を整えようとしたもの。今の銀座は火災で焼失した後由利公正により意図的に造られた 意次ではなく意次の家臣が収賄していた 意次の士分に拘らない態度は民間を活性化した 一揆ではなく徒党が禁止されており、一揆は為政者の批判として機能した 農民は刀狩後も士分としての帯刀は禁じられたが武器所持は認められていた2020/09/28
マカロニ マカロン
5
個人の感想です:B+。昭和47 (1972)年版中学校歴史教科書と34年経った平成18(2006)年版のもので記述内容がどのように変わり、なぜ変わったのかが丁寧に書かれていてわかりやすかった。私の中学時代は1960年台なので、前者に近いので、「三内丸山遺跡」はまだ発掘されてないし、聖徳太子像、源頼朝像、武田信玄像など無批判に信じていたが、現在の教科書では「伝えられる肖像画」となっているらしい。さらに、足利尊氏像に関しては完全否定されていて衝撃的だった。最近の歴史教科書を読んでみたいと思った。2018/07/26