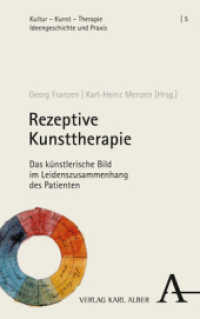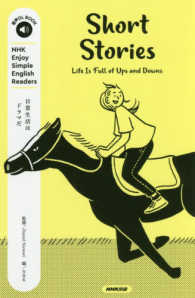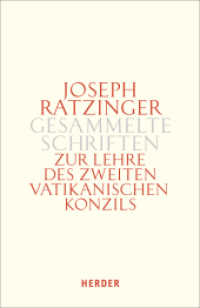内容説明
その昔、日本には、笑いを神にささげる人々がいた。それが日本の「笑い文化」の始まりだった。柳田国男が「烏滸の者」と呼び、その消滅を嘆いた人々―。歴史のなかで、さまざまに姿を変えて、彼らはどこへ消えたのか?日本文化の源流に深く分け入り、「笑い」の起源や歴史的変容を掘り起こした労作が、現代の「薄っぺらな、商品としての笑い」と強張りに満ちた社会を照射する。
目次
第1章 笑いの起源をたどってみれば
第2章 神と笑いと日本人
第3章 「笑い神事」に秘められた謎
第4章 共同体の変容と「笑い」の変化
第5章 都市化・近代化と笑いの変遷
第6章 グローバル化社会と烏滸の者
第7章 「笑い」に挑んだ知の巨人たち
第8章 災害の国日本と「無常の笑い」
著者等紹介
樋口和憲[ヒグチカズノリ]
1959年、東京都生まれ。東京都立大学(現・首都大学東京)法学部卒業。独立行政法人日本学術振興会国際事業部勤務を経て、同ワシントン研究連絡センター副所長、ボン研究連絡センター副所長を歴任。アメリカおよびドイツの学術動向調査、学術関係機関との調整業務などに従事した。現在、独立行政法人日本学術振興会学術システム研究センター専門調査役を務める。論文『蟻のベルクソン、手話する哲学者―進化に「生命の跳躍」を見た男』で第六回涙骨賞最優秀賞(中外日報社)を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
やま
3
第5章末尾「笑いの都市化のなかで」の中で軽く触れられた、〈市(バザール)〉で物売りの女性が生み出す笑いの歴史的経緯の説明が印象的だった。朝市などでのおばちゃんとの掛け合いが、日本の笑いの文化の重要な局面を担っていることを知ると、買い物がもっと楽しくなる!2014/05/18
れどれ
2
筆者の個人的主張は自身の世代を肯定するあまり自家撞着に陥っているとしか捉えられず共感も好感も持てはしなかったが、民俗学の領分に触れだすと俄然話が面白い。柳田国男の論説の抜粋、とりまとめからの時点で感興できるし、またそれらと自身の仮説とを接合させるアプローチも見事で、序文と結論を除いてはずっと心躍らせてもらった。2018/11/28
13km
2
昔の人々は笑いというものに並々ならぬ思いがあったのですね。今の芸人さんも面白いということですごくいい扱いされてますし、実生活でも面白い人は人気者ですものね。これからの日本はもっと笑いがある国になるように自分自身も面白い人を目指します。2013/10/22
果てなき冒険たまこ
1
烏滸の者という存在を規定したのに論が進むに連れてその存在意義がどんどんわからなくなる。1つの論をまとめるのに時代があっち行ったりこっち行ったりで何がなにやら。 面白くなかった。2022/08/15
ず
0
オコゼを持ち歩きたい気持ちになった。2014/01/18
-
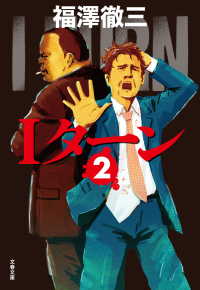
- 電子書籍
- Iターン 2 文春文庫