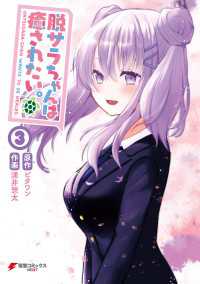出版社内容情報
若手研究者のフィールドワークを紹介するシリーズの第3弾。北は北海道から南は沖縄まで日本の鳥類に関する研究者の奮闘に迫る。若手研究者のフィールドワークを紹介するシリーズの第3弾。北は北海道から南は沖縄まで日本各地のフィールドで鳥を対象として活動する若手研究者14名が、鳥ならではの調査・研究の難しさや醍醐味を交えながら紹介する。
はじめに 北村 亘
1 ツルの舞が語りはじめてくれたこと 武田浩平
きっかけは双眼鏡と読書/偶然と必然に導かれて―研究室と対象/釧路に降りる―初めの一年間/ダンスの収集/鶴のおとなたちは皆踊る―不可思議な謎/結果と反響/物語はまだ始まったばかり
コラム 鶴のいる情景を見守る―市民調査の勧め
2 利尻島でのウミネコ調査 風間健太郎
3 渡り鳥を追いかけて ―マガンの中継地利用調査 森口紗千子
きかっけ/鳥の先生がいない/マガン研究への誘い/宮島沼へ/脂肪蓄積の指標作り/捕獲/指標の検証/季節による渡りのちがい/博士号取得、それから/再び鳥類研究へ
コラム フィールドでの地域貢献
農業の変化により、マガンは害鳥に/食害対策あれこれ/地域貢献のさまざまなかたち
4 恐い鳥と幻の鳥 高橋雅雄
きっかけは野鳥クラブ/初めての研究対象チゴハヤブサ/大学進学と研究テーマ/水田の恐鳥ケリ/恐鳥を捕まえられるか/心機一転の博士課程進学/幻の鳥オオセッカ/幻の鳥との暮らし/幻の鳥を捕まえる/幻の鳥を観察する/幻の鳥を数える/幻の鳥の未来
コラム:オオセッカの巣の動画撮影
5 スズメの研究―意外と知られていない身近な鳥の生態 加藤貴大
はじめに/フィールドとしての都市部―スズメプロジェクト/スズメの巣探し―フィールドワーカーは不審者?/電柱に巣食うスズメ―ヒトがスズメに巣場所を提供している?/新潟県大潟村での調査―やはりスズメ/フィールドとしての大潟村―フィールドワークの成果はフィールドの質で決まる?/びっくり箱―巣箱と使ったフィールドワーク/オスは死にやすい―スズメの未孵化卵の謎/秋田弁の壁―老人と「なまはげ」/フィールドワーカーとフィールドの人々の利害関係/フィールドワーカーの「隠す」行動/最後に
コラム スズメ捕獲記―スズメvs私
6 街のツバメで進化を調べる 長谷川 克
ツバメという鳥/「性選択」による進化/街なかでの調査/夜の調査/街なかのツバメの特性と予想外の結果/繁殖が早いオス、遅いオス/なわばりとオスの見た目/可愛さという魅力/まとめ
コラム 目的にあった対象種を選ぶ
7 絶海の孤島に通いつめた日々 安藤温子
研究を始めたきっかけ/はじめての小笠原/幻のハト/毎月の小笠原通い/島々と飛び回るハト
コラム 小笠原諸島でフィールドワークの裏側
8 バイオロギング海鳥学 山本誉士
オオミズナギドリとの出会い/はじめてのフィールドワーク/無人島でのフィールドワーク/海外での海鳥調査/仮説検証型とデータ先行型/フィールドワーク事始/こだわらないというこだわり
コラム フィールドワークとコミュニケーション能力
9 雲上で神の鳥を追う 小林 篤
日の出との勝負/ライチョウとの出会いまで/ライチョウとは/日本に生息するライチョウの特徴/高山での調査が始まる/山小屋での生活/季節によって変わるライチョウの食性/進学という選択/新たな研究テーマ/調査員、土木作業員そして飼育員/日本の高山は美しい/おわりに
コラム 春山調査における装備について
10 鳥博士のキビタキ暮らし 岡久雄二
幼少期/夢中ですごした学生時代/キビタキとの出会いと直面した困難/繁殖地での生活/キビタキの生態/キビタキの羽の色の不思議/これからの研究
コラム 野外調査の安全管理
11 コウノトリが運んだ“つながり” 武田広子
野鳥との出会い/コウノトリとの出会い/豊岡でのコウノトリ野外調査―採食行動の観察/コウノトリ野外調査から、コウノトリ飼育員へ/スウェーデンでシュバシコウ飼育/再び、豊岡のコウノトリ/おわりに
コラム コウノトリの野外調査に必要なもの
12 ブッポウソウ 黒田聖子
13 南の島に移り住んだモズの生活を追う 松井 晋
鳥類に興味をもったきっかけ/大学院の研究生活/亜熱帯に定着したモズを追って/モズの繁殖生態を調べる/南大東島でのフィールドワークをとおして
コラム 鳥マラリア感染症の検査
14 白いアイリングの中を覗け―亜熱帯の森にメジロを追った十年間 堀江明香
蛙の子は蛙か/外れ値の父と母をもつと…/海想/メジロ屋人生のはじまり/かばかりの 調査となりし 四年坊/南の島と初夢/うふあがりじま/孤島のメジロの気持ちを探る/子育ての鍵は父親だった/おわりに
コラム 巣探し職人への道
武田 浩平[タケダ コウヘイ]
著・文・その他
風間 健太郎[カザマ ケンタロウ]
著・文・その他
森口 紗千子[モリグチ サチコ]
著・文・その他
高橋 雅雄[タカハシ マサオ]
著・文・その他
加藤 貴大[カトウ タカヒロ]
著・文・その他
長谷川 克[ハセガワ マサル]
著・文・その他
安藤 温子[アンドウ ハルコ]
著・文・その他
山本 誉士[ヤマモト タカシ]
著・文・その他
小林 篤[コバヤシ アツシ]
著・文・その他
岡久 雄二[オカヒサ ユウジ]
著・文・その他
武田 広子[タケダ ヒロコ]
著・文・その他
黒田 聖子[クロダ セイコ]
著・文・その他
松井 晋[マツイ シン]
著・文・その他
堀江 明香[ホリエ サヤカ]
著・文・その他
目次
ツルの舞が語り始めてくれたこと
最北の島でウミネコをみる
渡り鳥を追いかけて―マガンの中継地利用調査
恐い鳥と幻の鳥
スズメの研究―意外と知られていない身近な鳥の生態
街のツバメで進化を調べる
絶海の孤島に通いつめた日々
バイオロギング海鳥学
雲上で神の鳥を追う
鳥博士のキビタキ暮らし
コウノトリのハチゴロウが運んでくれた“つながり”
青い鳥ブッポウソウを追いかけて―ゲゲゲ…謎の生態に迫る
南の島に移り棲んだモズの生活を追う
白いアイリングの中を覗け―亜熱帯の森にメジロを追った十年間
著者等紹介
武田浩平[タケダコウヘイ]
1988年生まれ。総合研究大学院大学先導科学研究科博士課程修了、博士(理学)。専門:動物行動学、保全生態学、鳥類学。動物の複雑なコミュニケーションが中心テーマであり、対象はタンチョウ。現在(2018年)は総合研究大学院大学の特別研究員
風間健太郎[カザマケンタロウ]
1980年生まれ。北海道大学水産科学院博士課程修了、博士(水産科学)。専門:海洋生態学、行動生態学、保全生態学、地球化学。日本学術振興会特別研究員(受入:名城大学)を経て、現在は北海道大学水産科学院博士研究員。2016年度日本鳥学会黒田賞受賞
森口紗千子[モリグチサチコ]
1981年生まれ。東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了、博士(農学)。専門:景観生態学・保全生態学。(独)国立環境研究所特別研究員、(独)農研機構動物衛生研究所農研機構特別研究員、新潟大学特任助教を経て、現在は日本獣医生命科学大学ポストドクター
高橋雅雄[タカハシマサオ]
1982年生まれ。立教大学大学院理学研究科博士課程後期課程修了、博士(理学)。専門:農地棲鳥類(ケリ・トキなど)や湿性草原棲鳥類(オオセッカ・コジュリン・シマクイナなど)を対象とした行動生態学と保全生態学
加藤貴大[カトウタカヒロ]
1987年生まれ。総合研究大学院大学先導科学研究科博士課程修了、博士(理学)。専門:行動生態学。幼少から親の仕事の都合で東京、北海道、秋田県を転々とし、両親の出身である秋田県で小中学生時代をすごした。学部時代に分子生物学の基本を学んだ後、スズメの生態を研究する
長谷川克[ハセガワマサル]
1982年生まれ。筑波大学大学院生命環境科学研究科博士課程修了、博士(理学)。専門:行動生態学・進化生態学。ツバメなどの美しさ・可愛さの進化を研究している。2017年度日本鳥学会黒田賞受賞
安藤温子[アンドウハルコ]
1986年生まれ。京都大学大学院農学研究科森林科学専攻博士課程修了、博士(理学)。専門:分子生態学、保全生態学。小笠原諸島に生息する絶滅危惧鳥類の保全に関する研究をしてきた。最近は霞ヶ浦のカモ類も扱っている。現在は国立研究開発法人国立環境研究所研究員
山本誉士[ヤマモトタカシ]
1983年生まれ。総合研究大学院大学複合科学研究科極域科学専攻五年一貫制博士課程修了、博士(理学)。専門:行動生態学・バイオロギング・環境動態解析。国立極地研究所国際北極環境研究センター特任研究員、日本学術振興会特別研究員PD(名古屋大学大学院環境学研究科)を経て、現在は統計数理研究所で特任研究員として動物の移動・空間利用に関する研究に取り組んでいる
小林篤[コバヤシアツシ]
1987年生まれ。東邦大学大学院理学研究科博士後期課程生物学専攻修了、博士(理学)。専門:保全生態学、個体群生態学
岡久雄二[オカヒサユウジ]
1987年生まれ。立教大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。専門:鳥類生態学、再導入生態学。キビタキの生態研究のほか、ニューカレドニアの固有鳥類の保全、トキ野生復帰事業に携わる。現在は環境省佐渡自然保護官事務所希少種保護増殖等専門員
武田広子[タケダヒロコ]
1981年生まれ。東邦大学大学院理学研究科生物学専攻博士前期課程修了、修士(理学)。専門:保全鳥類学。コウノトリ飼育員を経て、現在は豊岡市立コウノトリ文化館自然解説員としてコウノトリ野生復帰事業についての普及・啓発を行いながら、コウノトリ市民レンジャーとしてコウノトリの野外調査を行っている
黒田聖子[クロダセイコ]
1988年生まれ。兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科博士後期課程。専門:鳥類生態学。現在、ノートルダム清心学園清心中学校・清水女子高等学校に常勤講師として勤務しながら、岡山県でブッポウソウの研究活動を行っている
松井晋[マツイシン]
1978年生まれ。大阪市立大学大学院理学研究科後期博士課程修了、博士(理学)。専門:動物生態学。おもに鳥類の生態、生活史進化に関する研究を行っている。現在は、東海大学生物学部の講師として、北海道と沖縄をフィールドに研究を続けている
堀江明香[ホリエサヤカ]
1981年生まれ。大阪市立大学大学院理学研究科後期博士課程修了、博士(理学)。専門:鳥類学、行動生態学。卒業研究から一貫してメジロの研究を続けている。現在のテーマは、子育て戦略の進化メカニズムの解明(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。