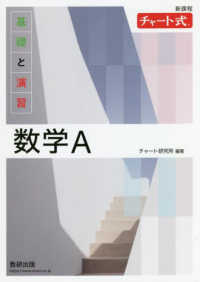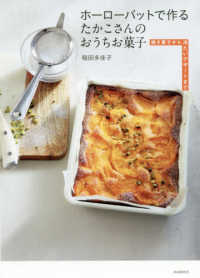内容説明
生命のつながりに感謝。日本独自の動物観や生命観を映しだす供養碑にまつわる37のものがたり。
目次
1部 祀られた魚と供養の多様性(サメ―サメとジンベイザメ;マグロ―マグロの大漁に沸き、被爆マグロに泣く;サケ―サケ漁とサケの人工ふ化;ブリ―ブリの群れによせる想い;ニジマス―アメリカ産まれの魚と供養 ほか)
2部 碑と時代性(中世以前―ナマズを祀る;中世―行基伝説とコイの霊験;中世―宇治川の十三重石塔と殺生禁断;中世―海から出現する神仏たち;近世―いさな獲る浜のにぎわいの証言者 ほか)
著者等紹介
田口理恵[タグチリエ]
博士(学術)。文化人類学。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了。国立民族学博物館・地域研究企画交流センターCOE研究員の後、東京大学東洋文化研究所、総合地球環境学研究所での研究を経て、2005年より現職。現在、東海大学海洋学部海洋文明学科准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。