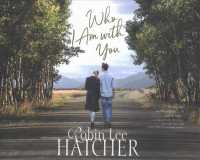内容説明
なぜ日本人は降車駅に着くと、突然ニョキっと起きあがるのか?ケンブリッジ大学の文化人類学者が論じる、日本人の居眠りに学ぶ、智恵と効果。
目次
01 日本人の睡眠習慣
02 日本の睡眠―昔と今
03 ところ変われば睡眠習慣変わる
04 睡眠と余暇
05 居眠りの社会的ルール
06 居眠りの社会学
07 居眠りの効果―賢くなるための短眠法
著者等紹介
シテーガ,ブリギッテ[シテーガ,ブリギッテ] [Steger,Brigitte]
1965年オーストリア生まれ。ウィーン大学日本学研究所にて睡眠に関する研究で博士号(日本学)取得。その博士論文で2002年度オーストリア銀行賞を受賞。現在はケンブリッジ大学東アジア研究所の准教授として、日本の日常生活を研究している。近年は東日本大震災で被災した岩手県山田町の人々とともに暮らし、聞きとり調査も行っている
畔上司[アゼガミツカサ]
1951年長野県生まれ。東京大学経済学部卒。日本航空勤務を経て、現在ドイツ文学・英米文学翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こばまり
40
何が驚いたって、私達の日常のウトウトを20年も研究してくださった外国の方が居られるということです。保育園のお昼寝の時間、川の字で寝る親子、最寄り駅でパッと目覚めるサラリーマン、居眠り姿が中継されてしまう国会議員等等、全てがエキゾチック・ジャパンなのだなと。ちなみに原題は只の「INEMURI」。2014/06/21
gtn
33
電車内、会議中、国会開会中等どこででも居眠る日本人が、外国人には奇異に見えるらしい。もともと他国に比べ睡眠時間が短い上、シエスタの習慣もない。なにも真剣に横になって休むのではない。居ながらにして眠るというのがいじらしいではないか。そんな日本人を著者は好意的に眺める。2018/11/12
いちろく
24
この本によると日本国外で唯一日本人の居眠りについて研究している著者の本。居眠りについて、健康や効率の面からではなく、どの様に眠っているのかについて観察された報告書的な内容。タイトル通り、外国人の視点から、日本人の睡眠と居眠りについて書かれており興味深く読めました。外国の居眠り研究者の方の目からは、このように見えるのだなと。深く掘り下げられた内容ではなく、小説感覚であっさりと読めた点は少し残念。2014/11/28
Nobu A
21
久々の更新。HONZ推薦本。13年刊行。ケンブリッジ大学東アジア研究所教授が日本人の居眠りを論考し大変興味深い。外国人ならではの客観的視点。抑「居眠り」の語源など考えたこともなかった。布団使用での有効活用と親子で寝起きを共にする習慣との関係性やゴッフマンの主要・副次関与と支配・従属関与の援用での捉え方等、とても面白い。他方、翻訳のせいか「塾は私立であり」の表現は明らかに変。公立の対比として使うもの。また「多くの教員は何人かが眠っていると喜ぶ」ってそんな訳はない。校正で苦言を呈する日本人はいなかったのか。2023/07/09
Uzundk
16
居眠りは悪という認識を打ち破る。まず前提として著者の文化圏では単相睡眠、夜は寝て昼は起きる習慣で、途中で寝ることは推奨されない。そんな視点からみた日本の睡眠事情、昼寝を推奨したり居眠りを許容する文化はどういう意味を持つかを考える。中身としてはインタビューや過去文献の引用があり社会学的な話で生理学的な検証はないので注意。 居眠りは日本特有では無く欧州ではシエスタの国もあるし気温の高い地域では推奨してたりもする、睡眠習慣とは文化的なものである。2015/04/02
-

- 電子書籍
- 美少女学園 眞辺あみ Part.52 …
-

- 和書
- 地味にすごい授業のチカラ