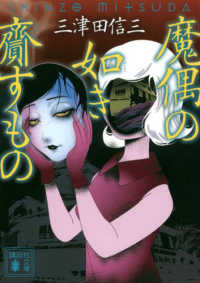内容説明
「吾れ唯足ることを知る」の精神に学ぶ、サステナブルな未来を守るために私たちが今できること。アメリカ人研究者が見た地球を守る江戸人の知恵。斬新な物語と自筆のイラストで、江戸の先進的なエコ生活を解き明かす。
目次
1章 田畑と森に囲まれて自給自足で生きる農民の豊かな暮らし(地形を最大限に生かした稲作の知恵;豊かな水の恵みをシェアする ほか)
Lesson1 江戸時代の農民の暮らしから学べること
2章 大いなる工夫でサステナブルに暮らす町人を訪ねて(きれいな道、緑の町並み;活気あふれる日本橋の魅力 ほか)
Lesson2 江戸時代の町人の暮らしから学べること
3章 実用的な美を重んじる武士の哲学に触れる(安らぎと風情が感じられる武士の屋敷;玄関に見る威厳ある調和 ほか)
Lesson3 江戸時代の武士の暮らしから学べること
著者等紹介
ブラウン,アズビー[ブラウン,アズビー][Brown,Azby]
1956年生まれ。金沢工業大学未来デサイン研究所所長。1985年より日本在住。イエール大学で日本建築を研究した後に来日し、1988年、東京大学大学院工学部建築学科修士課程を修了。日本の建築やデザインについて記した著書がある
幾島幸子[イクシマサチコ]
1951年東京生まれ。早稲田大学政経学部卒。翻訳家。ノンフィクションから児童書まで幅広く手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Squirrel
20
NHKの週刊ブックレビューで紹介され気になっていた本。農民・町人・武士のそれぞれのエコ的生活の紹介。これを書くにあたっての膨大な資料をとりまとめたことについて、まず感嘆する。並大抵な作業ではなかったと思う。内容については町人の章が一番読み応えがありました。「できあいの惣菜を後ろめたく思わない」というところを読むのが目当てだったが、12行で終わってしまってちょっと残念。もう一歩踏み込んで現在の生活に応用できる具体例があるともっと良かった。そして、実は最初から最後まで内容がイメージしずらくて読むのが大変でした2011/09/18
aisapia
13
江戸は自然と共存していたんだなと思いました。生きるために自然と共存していたし、それが生きるために必要だとわかっていたのに、いつそれを忘れてしまっただろうか。。なんでも再利用を念頭に物を作ったり、だからこそ物を大切に作ったりと、学ぶことばかりです。今からこの江戸の世界には戻れないけど、江戸の考え方を心に留め置いて生活するだけでも違うんじゃないかと思うので読めてよかった。2021/02/10
1.3manen
10
2009年初出。謙虚さを尊び、浪費を嫌い、協力による解決を求め、一人ひとりが必要な分だけを手に入れ決して決してそれ以上を求めない(013頁)。詳しいデッサン付きの解説がうれしい。江戸時代の循環型社会は合理的であって、文明というものの意味を考えさせられる。自給自足に、森の管理。江戸時代の人びとの知恵の凝縮が本書には詰められている。1970年代にオーストラリアで始まったというパーマカルチャーも紹介(097頁)。江戸の人口は≒130‐140万人と今の100分の1程度(114頁)。維持可能な社会を江戸人に求める。2013/05/30
Nobu A
9
金沢工業大学未来デザイン研究所所長が江戸時代の庶民の質素な生活や優れた武家屋敷から都市計画をアメリカ人として外の目から解説。ナレーション形式で当時の生活様式を目の当たりにして読んでいるようで新鮮。何よりも江戸時代の日本社会が自然に調和し、現代でも類を見ない環境に優しい生活をしていたのは誇るべき史実。環境問題が深刻化している昨今、江戸時代に戻ることはできないが、先人や歴史から学ぶことは多い。今度の新居に3畳程のベランダがある。読了後、そこで小さな野菜栽培を始めたくなった。個人レベルの環境配慮が大事。2015/07/31
宇花
7
サステナブル(持続可能な)社会、「足るを知る」という精神は江戸時代が最も顕著だったとのこと。そして、わたしが今考えていること(やりたいと思っていること)と同じことが書かれていて「わー!そうそう、これこれ!!こういうことなんだよ!!」と興奮した。誰もが生徒であり誰もが先生になれる。個々人の得意分野を集まった人たちに教えていく、伝えていく。能力や技術を共有していく、って、本当に大切なことだと思う。それを江戸時代の人たちは当たり前のようにしていた。とても素敵なこと。コメント欄に抜粋文章を記載させていただきます。2015/08/23