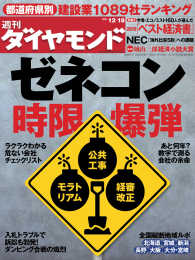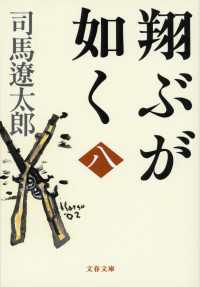内容説明
丸腰で、仕事はできない。あなたのアタマとカラダを『アイデア工場』に変えるとっておきのシンキング・ツール、教えます。
目次
序章 広告会社でも最初は「ただの人」。今からでも全く遅くない!
第1章 「アイデア」「企画」を考えるとは、何をすることなんだろうか?
第2章 どうしたら“必要な情報”が入ってくるのか?―情報が頭に入ってくる考具
第3章 展開・展開・展開!―アイデアが拡がる考具
第4章 企画=アイデアの四則演算!―アイデアを企画に収束させる考具
第5章 時にはスパイスを効かす!―行き詰まったときのアドバイス
第6章 あなただけの『考具』を見つけよう!
終章 頭の動き方がシステム化することこそ、本当の『考具』かもしれない
著者等紹介
加藤昌治[カトウマサハル]
1994年(株)博報堂入社。現在同社コーポレートコミュニケーション局勤務。情報環境の改善を通じてクライアントのブランド価値を高めることをミッションとし、マーケティングとマネジメントの両面から課題解決を実現する情報戦略・企画を立案、実施する毎日
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ehirano1
112
実は10年ぶりの再読で、「研究者の仕事術(島岡要)」で本書を知りました。著者が使用している「考具」を惜しみなく具体的に平易に記載されていて、かなり使える読者想いの構成でした。「聞く考具(=聞き上手になる効用と方法)」というのがあの『7つの習慣(コヴィ―&スキナー)』にあるとのことで慌ててかの名著を読み直し始めましたwww。2022/11/05
mura_ユル活動
87
【読みたい本読了】2003年の本。考えるための道具『考具』について、21ケ、紹介している。今だとクラウドを利用したサービスなども、ありそうだ。良いデザインは、まず、わがままで考え、使いやすいのかなど「思いやり」を次のステップで考える。どの道具も聞いたりして知っているが、カラーバスは知らなかったなあ。筆者のノウハウは、考具を使ってアイデアを出すことと、それを料理すること。それらがコンパクトにまとまっている。具体例は少ない。図書館本。2015/05/24
ehirano1
84
「キョロキョロする、だって立派なノウハウなんです。アイデアは普段の生活や仕事の中から生まれてくるものです(p14)」。仰る通りなのですが、昨今ではあんまりキョロキョロすると挙動不審で通報される可能性がるのでwww、電車などの移動時にスマホなんか見ずに外を見ると効果的だと感じてます。因みに、トンネルが多い区間では・・・諦めてスマホか読書ですwww。2025/02/09
ehirano1
76
「・・・その結果今回は使えない、と判断したものは捨てます。バッサリ捨てます。無理矢理入れようとすると、複雑になって失敗します。他の課題にハマる時が来ますから、しそれまではお蔵入り(p161)」。『バッサリ』というのと『他の課題にハマる時が来ます』というのがとっても大切ではないかと思います。前者には執着を放棄する勇気、後者では何の根拠もない事へも希望を持つ勇気が必要ではないかと思いました。2024/04/17
ehirano1
73
「・・・アイデアの作り方、その手法は至ってシンプルなんです。今も昔も変わらない。違うのはその方程式に入れるデータ。データは時代や環境に応じていつも新しく変わっていきます。だからアイデアが尽きるという、ということはありえません(p150)」。これには全く同感です。あと、なぜかアイデアにも「あるサイクル」があるように時折思うことがあります。もう一つ別の方程式があるのかな?2023/07/19