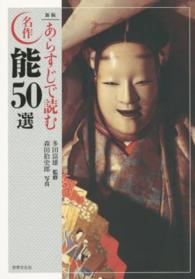出版社内容情報
戦後日本において、マイホームの購入を前提とする社会がどのように現れ、拡大し、どう変化したのか? 住宅政策の軌跡を辿り、住まいの未来を展望する。
内容説明
「持ち家」の持続可能性を問う。“結婚し、稼ぎ、家を買う”は続くのか?住まいから社会変化をみる。
目次
はじめに 大衆化から再階層化へ
第1章 住宅所有についての新たな問い
第2章 住宅システムの分岐/収束
第3章 持ち家の時代、その生成―終戦~一九七〇年代初頭
第4章 もっと大量の持ち家建設を―一九七〇年代初頭~一九九〇年代半ば
第5章 市場化する社会、その住宅システム―一九九〇年代半ば~
第6章 成長後の社会の住宅事情
おわりに 新たな「約束」に向けて
著者等紹介
平山洋介[ヒラヤマヨウスケ]
1958年生まれ。神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授。専門は住宅政策・都市計画。日本建築学会賞(論文)受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヒナコ
9
同著者の『「仮住まい」と戦後日本』を読んだついでに、本作も読んでみた。内容としては、『「仮住まい」と戦後日本』と重複した箇所が多くあり、戦後日本の住宅政策を知りたい人は、専門家でもない限りは、どちらか一冊で事足りるだろう。 本著の特徴としては、終戦から1970年代までの持ち家政策形成期(第3章)、1970年代から1990年代半ばまでの持ち家奨励促進期(第4章)、1990年以降の住宅が市場化・金融化される時期(第5章)と、戦後日本の住宅政策を三つの期間に分けて、歴史的考察をしている点だろう。→2022/01/14
まさこ
9
住宅政策の戦後史。現時点のの高齢者の持ち家率83.2%(2005、古いが)の高さが自己年金となっている、という要素は大きい(これはもっと認識されるべき)。そして本人が住まなくなった途端に金融価値にしか換算されない(地縁から離れた親子間では価値は継承されにくいので、ますますかな…)ので、その価値=立地になる(貧しい…)。住宅の金融化が社会プロジェクトとなってきた帰結である。人口減少と高齢化に対し、住宅ストックの価値を再発見するような、住宅の金融化以外の方向の政策というか、方策を探したい。2020/12/05
鵐窟庵
7
戦後の住宅政策を各種数字や制度に基づき変遷を分析する。戦後しばらくの間は社会福祉として住宅政策があったが、やがて家族制度や中間層へ国民を誘導するための方針が出てきた。さらにバブルの少し前から新自由主義的傾向の萌芽が見られる、バブル以降はさらに世代交代による、住宅取得の前提条件が世代にわたって格差を拡大するようになり、さらに新自由主義的傾向が加速する。不動産をふやし続ける「拡大家族」と今ある不動産を減価する「食いつぶし家族」、さらに賃貸だけの「賃貸家族」。生々しい現実の格差拡大に著者はその改善案を提案する。2020/10/30
ことぶき あきら
6
戦後日本の住宅政策は、持ち家取得を推進することによって、経済拡大と社会統合を保つことを目指した。しかし、住宅を取得するための住宅ローン供給は、雇用の長期安定と賃金上昇を前提としている一方で、持ち家取得推進≒持ち家を金融化するシステム≒新自由主義(的住宅システム)が推進されればされるほど、雇用の長期安定と賃金上昇が望めなくなり、私有住宅は大衆化から再階層化に向かう。また、自力で私有住宅取得することは個人主義を前提とする新自由主義的なイデオロギーに則したことである一方、家族主義とも結合した政策・制度にも立脚。2021/07/17
フクロウ
4
日本の住宅システム(≒法制)は、社会保障ではなく経済の問題として把握・組み立てられ、そしてその際には社会構成単位を核家族とし、持ち家を持った保守=中流をメインストリームとすることで自民党政権の支持を安定化させる目的も相まって、公共賃貸ではなく持ち家政策が、国家主導の開発主義モデルのもとで採用・導入されてきた。オイルショック以降、経済危機が起きるたびに住宅建設が景気刺激策として利用され金融化が進み、本来融資対象ではない低所得者をも取り込んでいった。結果起きたのがバブル経済の破綻と金融危機。2024/12/08