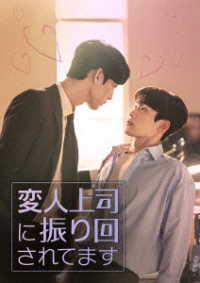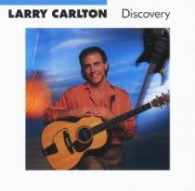内容説明
自分の「存在」を疑ったことはありますか?親から虐待されて育った人たちは、普通とは全く違う世界を生きている。そこから見えてくる、人間の心、存在、そして幸せの意味とは?
目次
第1章 もうこの世から消えてしまいたい(光の首飾り;被虐待児の人生から教えてもらったこと)
第2章 異なる世界で生きる人々(私には日にちがない;私には過去がない、それを返してほしい ほか)
第3章 児童虐待とはどういうものか(虐待かどうかの、二つの判定基準;虐待の継続性と異常性―虐待判定その1 ほか)
第4章 回復―一緒の世界でみんなと手をつなぐ(発達障害と誤診された被虐児、浩樹君の回復;生きる義務感を相対化する ほか)
第5章 心はさらに広い世界へ(社会的存在の範囲を生き直す;二つの存在を同時に生きる ほか)
著者等紹介
高橋和巳[タカハシカズミ]
精神科医。医学博士。1953年生まれ。慶應義塾大学文学部を中退、福島医科大学を卒業後、東京医科歯科大学の神経精神科に入局。長く都立松沢病院に勤めて精神科一般の診療の他、精神科救急やアルコール専門外来、家庭内暴力・拒食症・引きこもり等の家庭内問題に関わってきた。同院精神科医長を退職後は都内でクリニックを開業し、診療を続けている。またカウンセラーの教育にも熱心で、スーパーヴィジョンを行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
29
人間を強くするもの、生きる上で支えになるものは愛だの希望だのじゃない。痛めつけられた瞬間に幼い身体、小さな心に芽生える「いつか必ずぶっ殺してやる」というきもちだけが人を強くすると今でも確信しているけれどそうした憎悪により自分を支えることが出来なかった子たちがたくさんいることを思うと胸が痛む。僕自身も自分自身に何の価値も見出せないし未だに生きる意味は皆無だけれど幸運なことに祖母に引き取られ生きる力を与えられた。いつか強くなれないままでしゃがみこんでいるガキどもを救ってやりたい。憎む力と強さを与えてやりたい。2017/09/06
そふぃあ
24
カミュを読んでから、「あぁ、私も異邦人なんだろうな。いつか排除の対象になってしまうかもしれないな」と思って生きてきた。暗闇の中を、時々差す光を頼りに歩いてきた。被虐児たちがこちら側を自称して呼ぶのはまったくぴったりな呼び名だと思う。不条理に暴力をうけるんだから。でも、処刑される人々を医者の目線で「異邦人」と呼ぶのはモラル的にどうかと思うよ。描かれていることには概ね納得し読む価値もあるが、上記の一点でその価値は大きく損なわれている。2019/07/18
ロア
24
タイトルが刺激的過ぎるので、手に取るのがはばかられますよね〜〜(; ̄∀ ̄;)でも、読んで損は無いと思います。10人居ればそのうちの一人は…と考えると、決して少なくはないのだなぁ。***教師、カウンセラー、精神科医、職場の管理職の方等にぜひ読んで頂きたい本だと感じました。2015/11/15
ロア
23
回復方法が二通り述べられているが、自力での回復はやはり難しそうだし、高橋先生のように被虐待者への理解が深く、薬以外の治療方法も組み合わせてくれる主治医に巡り会うことも難しいだろう。とりあえずこれからも、なんとか無事に生きてゆくしかないんだな。でも、本書で擬似カウンセリング出来たし、滅多にない感情共有も出来たのは嬉しかった。気になったのは被虐ママ。子供との触れ合いを通し回復する手段はあるというが、それがなされなければ負の連鎖は永遠に続く…子供が可哀想だ。義務感、緊張感、自責感、焦燥感に注意。ゆっくりを意識。2015/11/29
たんたん麺
22
「あ、そうだ。僕はいつも先のことばかり考えて生きてきたんだ!」「僕はまた、大切な時間を逃してしまった。大切な思い出を逃してしまった」心に引っかかっていたものがはっきり見えた。生き急いできた自分が見逃してきたものが見えた。それは人とのつながりだった。「過ぎ去った時間を取り戻したいと思ったのは、生まれて初めてだった。いつもいつも未来が不安で生きてきた。とにかく、次をこなすことで精一杯だった。義務感と恐怖だけで生きてきた自分のことがいま分かる。ずっと怖かったのだ。不安だったのだ。自分がかわいそうになった」2014/10/28