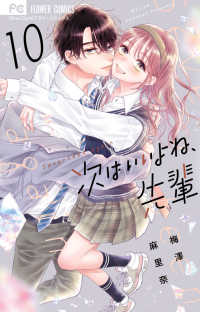出版社内容情報
中央ユーラシアが求めたのは侵略ではなく交易だった。古代から現代まで、世界の経済・文化・学問を担った最重要地域の歴史を描く。
クリストファー・ベックウィズ[ベックウィズ,クリストファー]
斎藤 純男[サイトウ ヨシオ]
目次
英雄とその友たち
二輪馬車の戦士たち
王族スキュタイ
ローマと中国の軍団
フン族の王アッティラの時代
突厥帝国
シルクロード、革命、そして崩壊
ヴァイキングとカタイ
チンギス・カンとモンゴルの征服
中央ユーラシア人、ヨーロッパの海へ
道は閉ざされた
中心なきユーラシア
よみがえった中央ユーラシア
バルバロイ
著者等紹介
ベックウィズ,クリストファー[ベックウィズ,クリストファー] [Beckwith,Christopher I.]
インディアナ大学中央ユーラシア研究科教授。中央ユーラシアおよび東アジアの歴史・言語・思想に通じ、いくつもの新しい見解を提出している
斎藤純男[サイトウヨシオ]
東京学芸大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
4
交易と遊牧で繁栄した中央ユーラシア諸国が、ヨーロッパ、中国、ロシアといった周辺地域に徐々に侵略され消滅するまで。フン族・モンゴル帝国など野蛮と恐怖のイメージが強いが、実際は交易を求める人々であり、周辺地域からの侵略に対する反撃として武力を使ったこと。また彼らの文化的影響はユーラシア中に及び、それは日本にも及んでいることが示されている。後半、「モダニズム」に対する強い批判を行っており、この辺りは意見が分かれるのではと思う。2017/04/16
ポルターガイスト
3
中央ユーラシアの歴史的意義は少なく見積もられている。インド・ヨーロッパ語族の拡大や殷周の起源を考えれば中央ユーラシアこそが農耕文明の起源と言っても過言ではない。その残虐性や貧しさは農耕文明により戯画的に誇張されている。実際には遊牧社会は多様であり,しばしば農耕国家よりも豊かであった。彼らが農耕国家と戦うのは交易の制限を解くためであり,それは近代の西欧諸国の態度と変わりない。などの主張は面白く歴史観を塗り替えられる快感がある一方で,事実関係の確認部分が多くそこは退屈。モダニズム批判の箇所は賛否ありそう。2025/08/08
めーてる
0
とてもとても興味深い本。それまで中央ユーラシアの人々について抱いてきた固定観念が、いかにヨーロッパ・中国中央史観によるものだったのかがよくわかる。もっと詳しく知りたいなあと思わされた。2017/11/02
-
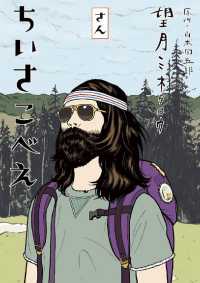
- 電子書籍
- ちいさこべえ(3) ビッグコミックスス…
-

- 電子書籍
- ヴァンパイア騎士(ナイト) 7巻 花と…