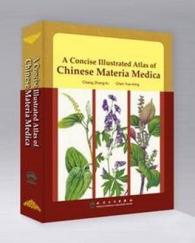出版社内容情報
民藝運動家の著者が、世界各地の風土と暮らしの中から生まれ、受け継がれてきた美しい道具類や雑貨の数々を紹介する。待望の復刊。カラー写真多数。
内容説明
暮らしの中の美しいものたち。世界中の美しい工藝品を紹介。
目次
楽しい椅子敷―日本
色模様のむしろ―日本
たのもしいガラス器―日本
毎日の椀と碗―日本
スープによい焼物―日本・スペイン
湯沸しの王様―日本
鋏のいろいろ―日本・スウェーデン
小箱と菓子鉢―スイス・日本
たたみ草の円座―日本
竹篭のいろいろ―日本〔ほか〕
著者等紹介
外村吉之介[トノムラキチノスケ]
1898年滋賀県に生まれる。1925年関西学院大学神学部卒業、1945年まで日本基督教団教師のかたわら民藝運動に参画。1948年倉敷民藝館創設、同館長。1965年熊本国際民藝館創設、同館長。1993年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のっち♬
108
「用即日」のコンセプトに基づき世界中の美しい工藝品を集めて分かりやすく解説。使えば使うほど美しくなる実用性至上主義は道具の存在意義の本質でもあるし、どの工藝品にも通底する健やかな美しさには自分で作り出す愉しみが溢れている。西アジアの敷物類や西欧の籠類は全く古びない品の良さがあるし、中国の水汲み手桶の合理性には唸らされる。特に強烈な印象を残したのはインドの馬乗り人形、単眼の目が妙に優しい。3割くらいは日本のもの、種類のちがう動物が抱き合ったおもちゃは日本だけというのは面白い。極端な二元論以外は心地よい一冊。2024/04/27
りの
17
「あのとき この本」で谷川俊太郎さんが紹介されていた本。絵本ではなく、世界中の民藝品を写真と解説で紹介した本でした。著者は民藝品を「健康で無駄がなく威張らない美しさを備えてよく働く、良い友だち」と説明しています。食器や布物など普段から興味のあるものをじっくり楽しみました。子ども向けなんですが、子どもには民藝品の良さは難しいかもしれないなと感じました。2015/09/10
さたん・さたーん・さーたん
5
この本で紹介されている「友だち」に囲まれて暮らす生活は、どんなにすてきだろう。その「友だち」を慈しむ心を持つことも同じくすてきだ。我が家の食器棚に埃を被って眠る品々には申し訳なく思う。すこしずつ引っ張り出してやろう。2017/06/01
fukura
3
心に叶う美しいものを使う暮らし 2012/06/22
Miwa_N2
3
世界の民藝品の鑑賞方法を子供向けに読み解いた本だがなかなかどうしてあなどれない。深い造詣と民藝愛にあふれるコメントは、何度手にとっても新鮮で民藝というものの新しい発見に満ちてます2011/09/14