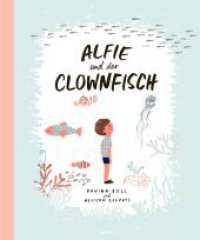内容説明
ナマコ―この奇妙に魅力的な生物の視座から、アジアと日本の歴史を眺めてみると、何が見えてくるだろう。アジアへの眼差しを深め続ける〈歩くひと〉鶴見良行が、十五年の熟成を経て、遂に完成した歴史ルポルタージユ大作。90年代の、新しい世紀のはじまりへ向けて、日本のゆくえを考える全ての読者に、いま開かれる。
目次
大平洋の島々(台所の実験;パラオ女性の教え;真珠とからゆきさん;クック船長の赤い羽;マニラメンとナマコ語;フィジーの混乱)
アボリジニーの浜辺(オーストラリア史の仕組み;東と西の谷間;マカサーンの出漁;揺れる国境;料亭バグースのこと;バッファローの旅;赤い靴の連想;墓に眠る人びと;階段踊り場の説)
〈東インド諸島〉の人びと(魔女;海港マカッサル;テルテナの領土;大きな踊り場;スルー;海賊と奴隷;華人)
漢人の北から(俵物三品;平民食;伊勢・志摩の串;風に飛ぶ仙人;アイヌ勘定;明治という時代;半島と列島;ゼラチン食の流れ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はる
6
カバー写真と書題に惹かれ購入していた本。スラウェシの女性がドラム缶に汲んだ海水でナマコを煮ている写真がとても印象的だ。ナマコ。果たしてナマコに視覚細胞があるのか?ナマコはヒト族を見るのか?そんな眼のないナマコを上代から現代の文献を渉猟し、南はオーストラリア北岸、インドネシア・スラウェシ州から始め東北アジア、各地のナマコ漁師訪ねヒト族とは何者ぞと問う。2024/09/21
小木ハム
3
世にも珍しいナマコを主体に置いた本。ただしナマコが主役ではなく、ナマコ視点で人の歴史を追いかけます。彼の前田利家も干しナマコが好きだった!歴史文書にはいつも英雄だけが載る。だからこの本を読むときは、自分がナマコになったつもりで読むと面白い。ヒトの醜さだったりアホらしさだったりを海底でぬぼーっと眺めてる・・・そんな俯瞰図。(俯瞰?)節々で著者鶴見さんの思想が二、三行で綴られるのですがこれは一読の価値あり。2017/03/28
紫電改
1
「バナナと日本人」が面白かったので、題名に惹かれて読んだ。文化人類学と海鼠の関係を平易に解説しておられてまぁまぁ楽しく読了。海鼠が輸出品であり高価な海産物であるということに驚いた。大昔から国境を越えた貿易があり、海鼠を加工して中国人がこれを買うという商流も面白い。トランプがやっている保護貿易主義は時代錯誤だなぁ、大昔からの交易が証明しているように思う2025/08/25
hideaki
1
世界史をナマコで辿っている。 食文化(加工方法、食べ方、価値) 南北問題(労働力、経営者、開拓、採取方法)2014/10/20
yagian
1
南太平洋から北海道まで広がるナマコ生産、交易の歴史を追った本。今、私自身、16世紀から19世紀のアジア交易の歴史に関心をもっているので、興味深い事実が提示されていた。しかし、この本は、日本語で書いて日本語話者に提供するというのはもったいないようにも思う。英語か中国語で、より広い読者に向けて書かれるべき本ではないだろうか。2014/04/20