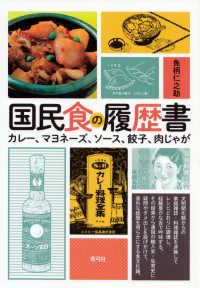出版社内容情報
古代ギリシアで哲学はどのように始まったのか。近年の研究成果を踏まえギリシア哲学史の枠組みを見直し、哲学者たちの思索を新たな視座から一望する記念碑的通史
内容説明
古代ギリシアにおいて、哲学はどのように始まったのか?そこで哲学者たちは、どのような問いを問い、思索を展開したか?こうした哲学の営みは、いかにして受け継がれてきたのか?資料論・方法論をふくむ最新の研究成果に目配りをし、これまでと大きく異なる枠組みと視点で、ギリシア哲学史の全体を俯瞰。33名の列伝体で描きだす通史。
目次
第1部 ギリシア哲学史序論(ギリシア哲学とは何か;ギリシア哲学資料論)
第2部 初期ギリシア哲学(ギリシア哲学の他者;総論―初期ギリシア哲学の枠組み;イオニアでの探究;イタリアでの探究;イオニアでの自然哲学)
第3部 古典期ギリシア哲学(総論―古典期ギリシア哲学の枠組み;ソフィスト思潮とソクラテス;ソクラテス文学とプラトン;アカデメイアとアリストテレス)
著者等紹介
納富信留[ノウトミノブル]
1965年生まれ。東京大学文学部哲学科卒業。同大学院人文科学研究科哲学専攻修士課程修了。ケンブリッジ大学大学院古典学部博士号取得。現在、東京大学大学院人文社会系研究科教授。著書に、『ソフィストとは誰か?』(2007年度サントリー学芸賞受賞)など多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
南北
52
プラトンの研究者である著者が哲学者32人を取り上げてギリシア哲学の通史を語る本。これまでも同様の本は出版されてきたが、まず哲学の定義から始めているのが目新しい。また、従来哲学者からは除外されてきたソフィストを哲学者の一員として扱い、ソクラテスとの関係を取り上げているところが興味深い。それぞれの哲学者の人物像や思想を述べているだけでなく、最後に「受容」という一節が設けられていて、後世に与えた影響を書いているのも特徴の1つだ。ヨーロッパへの影響が多いのは当然だが、江戸時代の蘭学者や芥川龍之介も登場する。2022/08/22
Gokkey
12
タレスに始まるイオニアの自然哲学からアリストテレス等のアカデメイア関係者まで、哲学者毎にその人生から思想まで紹介され、トリビア的な知識(例えばプラトンは四人兄弟の三男坊でレスリングをやっていた)を含めて興味深く読める。現代版のディオゲネス・ラエルティオスという位置付けが相応しいか?同じ時代を(やや強引な)ストーリーで描く日下部吉信氏の著書と方法論的に対極を成すように思えるが、リソースが限定的なせいか、両者の著書から伝わる世界観そのものに大きな相違は感じられない。プラトンとアリストテレスの項は特に秀逸。2022/09/16
みのくま
9
イオニアの自然哲学から南イタリア、ソクラテス文学、アカデメイア、アリストテレス、そして最後はシノペのディオゲネスまで通観する本書は、ギリシア哲学の繋がりが見えてきて大変興味深い。他方、他にも本書は多くのヒントが散りばめられているのだが、それらはぼく達読者に示唆されたままとなっており大変もどかしい読後感である。著者の厳選した哲学者たちは決して思索するだけの人物ではなかった。彼らとホメロスやヘシオドスといった詩人や、医学のヒポクラテス、歴史家のヘロドトス、そしてギリシア悲劇/喜劇作家たちと明確な境界はないのだ2024/01/05
nagata
6
完全読了には程遠いが、古代ギリシアで醸成され、以降西欧の世界観を作ってきたギリシア哲学の、とりわけ何を考え始めたのかあたりが大きく掴めたか。万物の根源を問い続け、不可分なもの=原子に辿り着いたのは必然だが、彼らは近代のように自然と切り離した人間像を措定していたわけではなかったように思う。もう少し踏み込んでみたい。2023/03/29
鴨長石
4
人物ごとにまとめたギリシア哲学の通史。ソクラテスの位置づけなど、従来のギリシア哲学史とは違う分類としているところもあるようだが、もともと予備知識もないのでどの程度革新性があるのかは自分にはわからない。著者はプラトン学者ということだが、プラトンよりもアリストテレスによりページを割いているのはどのような思想の表出なのだろうか。一度通読したあとは辞書のように使えるので自分のような哲学初心者にはありがたい一冊。ローマ時代を扱った続編も予定されているということで、楽しみに待ちたい。2023/03/15
-

- 和書
- 南朝迷路 文春文庫