出版社内容情報
ケアは、どうひらかれたのか?
「生き延び」と「当事者」の時代へと至る「心」の議論の変遷を跡付ける。
垂直から水平、そして斜めへ。時代を画する、著者の新たな代表作!
===
「現代は、ケア論の隆盛に代表されるように、人と人との水平的なつながりの重要性をいうことがスタンダードになった時代である。けれども、単に水平的であればよいわけではない。
水平方向は、人々を水平(よこならび)にしてしまう平準化を導いてしまうからだ。けれども、水平方向には日常を捉え直し、そこからちょっとした垂直方向の突出を可能にする契機もまた伏在している。ゆえに、垂直方向の特権化を批判しつつ、しかし現代的な水平方向の重視に完全に乗るわけでもなく、「斜め」を目指すこと……。
そのような弁証法的な思考を、精神科臨床、心理臨床、当事者研究、制度論的精神療法、ハイデガー、オープンダイアローグ、依存症といったテーマに即して展開したのが本書のすべてである。」
(あとがきより抜粋)
===
自己実現や乗り越えること、あるいは精神分析による自己の掘り下げを特徴とする「垂直」方向と、自助グループや居場所型デイケアなど、隣人とかかわっていくことを重視する「水平」方向。
20世紀が「垂直」の世紀だとすれば、今世紀は「水平」、そしてそこに「ちょっとした垂直性」を加えた「斜め」へと、パラダイムがシフトしていく時代と言える。
本書は、ビンスワンガー、中井久夫、上野千鶴子、信田さよ子、当事者研究、ガタリ、ウリ、ラカン、ハイデガーらの議論をもとに、精神病理学とそれにかかわる人間観の変遷を跡付け、「斜め」の理論をひらいていこうとする試みである。
著者は、2015年のデビュー作『人はみな妄想する』でラカン像を刷新し、國分功一郎、千葉雅也の両氏に絶賛された気鋭の精神医学者。デビューから10年、新たな代表作がここに誕生する。
【目次】
第一章 水平方向の精神病理学に向けて──ビンスワンガーについて
第二章 臨床の臨界期、政治の臨界期──中井久夫について
第三章 「生き延び」の誕生──上野千鶴子と信田さよ子
第四章 当事者研究の政治
第五章 「自治」する病院──ガタリ、ウリ、そしてラカン
第六章 ハイデガーを水平化する──『存在と時間』における「依存忘却」について
補論1 精神分析とオープンダイアローグ
補論2 依存症臨床の空間──平準化に抗するために
内容説明
空間の病理学。ビンスワンガー、中井久夫、上野千鶴子、信田さよ子、当事者研究、ガタリ、ウリ、ラカン、ハイデガーらの議論をもとに、「生き延びと当事者の時代」へと至る「心」の議論の変遷を跡付ける。ケアは、どうひらかれたのか?垂直から水平、そして斜めへ。時代を画する、著者の新たな代表作。
目次
第一章 水平方向の精神病理学に向けて―ビンスワンガーについて
第二章 臨床の臨界期、政治の臨界期―中井久夫について
第三章 「生き延び」の誕生―上野千鶴子と信田さよ子
第四章 当事者研究の政治
第五章 「自治」する病院―ガタリ、ウリ、そしてラカン
第六章 ハイデガーを水平化する―『存在と時間』における「依存忘却」について
補論1 精神分析とオープンダイアローグ
補論2 依存症臨床の空間―平準化に抗するために
著者等紹介
松本卓也[マツモトタクヤ]
1983年、高知県生まれ。2008年3月、高知大学医学部医学科卒業。2015年3月、自治医科大学大学院医学研究科修了、博士(医学)。2016年4月より、京都大学大学院人間・環境学研究科総合人間学部准教授。専門は、精神病理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sayan
うつしみ
msykst
tharaud
みき
-
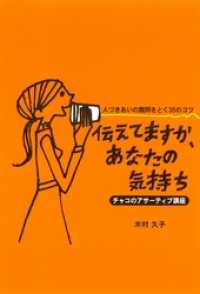
- 電子書籍
- 伝えてますか、あなたの気持ち : 人づ…








