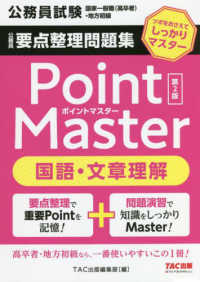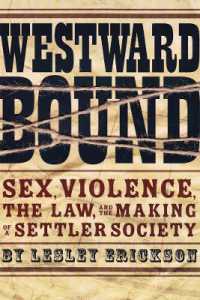出版社内容情報
ウィトゲンシュタインとスタンリー・カヴェル。ふたりの哲学者の議論を手掛かりに、人間の心というものに迫る。勇気に満ちた、古田哲学のあらたな一歩。
内容説明
ウィトゲンシュタインとスタンリー・カヴェル。ふたりの哲学者の議論を手掛かりに、ひとの心というものに迫る。懐疑論の悲劇を乗り越え、人間と関わりつづける勇気をくれる、古田哲学のあらたな一歩。
目次
第1章 他者の心についての懐疑論(「秘密の部屋」としての心;外界についての懐疑論 ほか)
第2章 懐疑論の急所(懐疑論の不明瞭さ、異常さ、不真面目さ;規準 ほか)
第3章 懐疑論が示すもの(懐疑論の真実、あるいはその教訓;生活形式への「ただ乗り」としての懐疑論 ほか)
第4章 心の住処(演技の習得;子どもが言語ゲームを始めるとき ほか)
著者等紹介
古田徹也[フルタテツヤ]
1979年、熊本県生まれ。2011年、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。新潟大学人文社会・教育科学系准教授、専修大学文学部准教授を経て、2019年より東京大学大学院人文社会系研究科准教授。「言語」「心」「行為」の各概念を手掛かりに、主に現代の哲学・倫理学を研究する。著書に『いつもの言葉を哲学する』(朝日新書)、『言葉の魂の哲学』(講談社選書メチエ、第四一回サントリー学芸賞(思想・歴史部門))、『それは私がしたことなのか』(新曜社)など多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
-

- 洋書
- Tamara