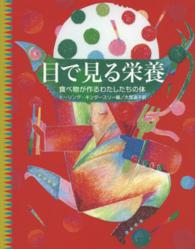内容説明
18歳から24歳の尾崎翠―新発見・全集未収録作品集。
目次
詩(迷へる魂;光と蛾;こだちの中)
短歌十一首
長篇詩(五時の汽笛;練馬の娘)
散文(冬のよ;夕陽;過去のうた;新緑の頃を;無題;海と小さい家と;山陰道の女)
著者等紹介
尾崎翠[オサキミドリ]
1896年鳥取に生まれる。女学校時代から詩歌・散文にすぐれ、「女子文壇」「文章世界」などへ投稿を始める。故郷で代用教員となった後、上京。1919年日本女子大に入学。在学中「無風帯から」を発表し、中退。文学に専念し、「第七官界彷徨」で注目される。1932年帰郷、消息を断つ。戦後、文学への再起を願いつつ果たせぬまま、「第七官界彷徨」が再発見された直後、1971年7月肺炎にて死去
稲垣真美[イナガキマサミ]
1926年2月京都府生まれ。東京大学文学部美学科を経て、1955年東大大学院美学専攻課程修了。現在、作家・評論家。代表作に「苦を紡ぐ女」があり、学習院女子短期大学、仏教大学で近代文学を講じた
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yn1951jp
28
若い尾崎の鋭敏な感性と美への憧れに触れるような作品群。色彩と光陰、季節と風土、日々の生活と思い出への愛着、尾崎の18歳から24歳頃の研ぎ澄まされた感覚世界を味わえる。美への強い憧れとそれを感得している自信のようなものを感じる。『哀詩』と銘打たれた「五時の汽笛(ふえ)」と「練馬の娘」、評論「山陰道の女」に描き出された『哀しい女の子(女)』の姿。これらは尾崎が後にめざした『自然主義から一廻転した心境文学、触覚文学』への出発地点なのだろう。「おぼえがき」(稲垣眞美)で尾崎再発見の過程を知った。2014/11/27
lonesome
19
「五時の汽笛」と「練馬の娘」の二篇を大正という時代を浮かべながら小説と思って読んでいて、言葉のリズムが素晴らしいなと思ったら長篇詩と銘打たれていたのでなるほど納得。 ―けれど、けれど過ぎゆくものは永遠に美しい。(「過去のうた」) ―『ゆけ、ゆけ、真の我に帰れ、そして一直線にそれに向つて走つてゆけ』(「海と小さい家と」) 詩人としての言葉のリズムを持っていた人だったんだなと散文を読んでもそう思う。2013/11/14
mass34
12
少女の年若く美しく純真な感性と、貧しいものの持つ一種の物悲しさをのせたリズムある文体とが相まって、読み手の胸にじわじわと染み込んでくる感じ。読みながら、子供の頃の何とも言えない不自由さも思い出す。美しく、胸のくるしい作品たちでした。2016/09/07
まる
11
詩はよくわからないのだけど、悲しさよりは寂しさを感じました。2014/04/05
Roy
10
★★★☆☆ 思いの他、純真すぎた。尾崎翠の詩、長篇詩、短歌、散文。少女誌に載せていた作品も多いせいか、汚れを知らない無垢な印象を受け、物足りなかった。「光と蛾」「夕陽」は、そこに儚さを感じたから好き。2008/12/29
-
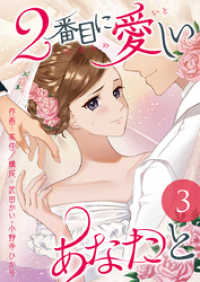
- 電子書籍
- 2番目に愛しいあなたと 3巻 Comi…
-
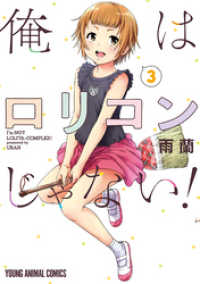
- 電子書籍
- 俺はロリコンじゃない! 3巻 ヤングア…