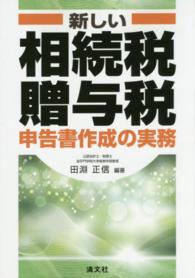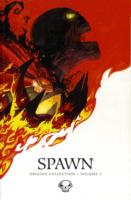出版社内容情報
表現とは何か、何を根拠にして表現を語れるのか・・・文学を始めとして、舞踏、装幀、建築のための数学まで、多種多様な角度から表現の本質を語る講演集。
内容説明
表現の深層へ向かって。文学、舞踏、装幀、色材、数学…多種多様な表現の本質を探る講演集。
目次
1(表現論;文学の原型について;物語の現象論;顔の文学)
2(文学の現在;文学の新しさ)
3(装幀論;舞踏論;色材論1;色材論2;色材論3;建築のための数学概論)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
30
死の考察が現代文学の基層(74頁~)。何が人間の存在の仕方なんだろうかということが文学における根本的な問題。最近舌に違和感があるけど、舌というのは喉の奥から出ている手だと考えると考えやすい(112頁)。義仲討ち死に。都で人望を失う。乱暴狼藉。庶民を苦しめる(129頁)。庶民を苦しめていいことはないです。義仲が好きだった女が都にいる。死ぬ前に会って死にたいと思う。2015/12/13
amanon
5
サブタイトルにやや丼勘定の感が(笑)。その半分は文学について語ったもの。ただ、前巻までの文学についての講演とはやや切り口が違っているとは言えるか。終盤の色彩論と数学論は殆ど字面を追っていただけというのが正直なところ。色彩論の冒頭は日本人の色認識についての解説で、それなりに興味深かったのだけれど、すぐに塗料についての専門的な話になり、化学式が出てきてからは、全く歯が立たず。とにかく絵の具にも歴史があるということは理解できたが。数学論では、吉本が高等数学ができる人をあまり評価していないのが印象的だったか。2019/07/03
金北山の麓で育って
1
【読み切れず】後半の色材論や数学論は無理、いったん読了。「文学の原型..」ハイデッガーとサルトルの死に対する考え方の違いは学生時代に読んだ「死の考現学」でも取り上げていたので懐かしい、「顔の文学」で近代未満の日本の文学は2種類に分けていかに今の我々には分からなくなったけれどどこかまだ我々自身に僅かかもしれないが実はキチンと地層に残ってるなんて面白い話しだ、今読むと微妙な感じがする「文学の現在」は射程を広げすぎな気がする、「文学の新しさ」では黒柳徹子も高橋源一郎を高く評価し過ぎで当時の時代の雰囲気を思い出す2024/09/01