出版社内容情報
「芥川・太宰・三島の「自殺」の運命」に始まり、三回にわたる『死霊論』、荒地派の詩、岡井隆の歌、中上健次、村上春樹、村上龍まで、戦後文芸を語った講演集。
内容説明
いま文学が負けるに決まっているのは自明に前提。三回にわたる『死霊』論を始めとして、三島由紀夫、中上健次、村上春樹、村上龍まで、文学の戦後と現在を語る。
目次
1(芥川・太宰・三島の「自殺の運命」;『死霊』について;中上健次私論)
2(荒地派について;詩について;物語性の中のメタファー;『神の仕事場』をめぐって;一行の物語と普遍的メタファー―俵万智、岡井隆の歌集をめぐって;個の想像力と世界への架橋)
3(文学の戦後と現在―三島由紀夫から村上春樹、村上龍まで;作品に見る女性像の変遷)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
酩酊石打刑
4
吉本の講演記録を、以前は早稲田の古本屋文献堂に行っては、簡易印刷された小冊子になったものを購入しては読んでいたものだ。80年に入る頃までは、吉本が太宰の文章について思っていたように、吉本の文章は一つ残らず読みたいと思っていた。3章に分類された二つの文章を、興味深く読んだ。「作品に見る女性像の変遷」という視点は、なかなか見かけることのない珍しいもののように思えた。2015/10/29
Takashi Kai
4
吉本隆明って言えば、ぼくらのような世代では、むしろ、よしもとばななのお父さんってイメージのほうが強いかな(ばなな、なんか受験で出たやつ以外読んだことないけど)。講演集である。特に、吉本隆明に興味があるわけでもないのだが、帯にやられて買った。だって、「死靈論をはじめとして、三島由紀夫、中上健次、村上春樹、村上龍」ってさ、本読みなら買っちゃうじゃん。内容的には講演集なので、くだけてて良い。まぁ、論評読みたいなら専門買ったほうがいいだろうしね。ビール飲んだりコーヒーやりながら読むにはいい本だ。2015/10/12
amanon
3
先に読んだ《戦前篇》に比べると、詩歌への言及は多かったというのが第一印象。とりわけ短歌は個人的に馴染みの浅い領域なので、正直とっつきにくかったが、その反面、短歌の世界でも革新的な試みが行われていたという事実は興味深かった。また、晩年の三島の保守反動的な傾向について、同時代を生きた吉本にとっても驚きであり、唐突であったという事実には驚かされたのと同時に納得もいった。それと本巻で度々言及される埴谷雄高への複雑な思いは、二人とも故人となった今となっては何とも言えない感慨を覚える。もうこんな人達は出ないだろうな…2019/06/10
Yoshihiro KONISHI
1
やはり吉本隆明は作家論が一番読み応えがある。2015/11/29
-
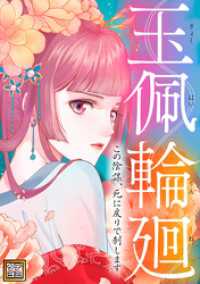
- 電子書籍
- 玉佩輪廻~この陰謀、死に戻りで制します…
-
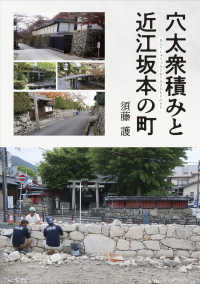
- 和書
- 穴太衆積みと近江坂本の町







