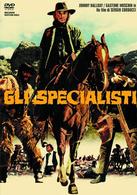出版社内容情報
医療が高度化した現在、受けるケアを決めるのは、本人?
医療者? 家族? QOL(生命の質)を軸に、人生百年時代の「よく生きる」を考える、生命倫理学入門。
内容説明
人生一〇〇年時代、高度な医療の恩恵にあずかる現代人。でも、医療は「魔法」?長生きだけが「幸せ」?高齢者のフレイル、地域包括ケア、看取り搬送…医療技術と人間性の接点を、QOLから考えてみませんか。Quality of Life(生活の質)から考える、生命倫理学入門。
目次
序章 QOLって何だろう
第1章 医療とQOL
第2章 高齢者医療とQOL―フレイルにどう対処したらよいか
第3章 認知症ケアとQOL
第4章 QOLを伝えられない人のQOL
第5章 家族と私のQOL
第6章 看取りとQOL
著者等紹介
小林亜津子[コバヤシアツコ]
東京都生まれ。北里大学一般教育部教授。京都大学大学院文学研究科修了。文学博士。専門は、ヘーゲル哲学、生命倫理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





TERU’S本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
タルシル📖ヨムノスキー
28
昨年12月に読んだ久坂部羊さんの〝日本人の死に時〟を受けての再読。「生命の質」「生活の質」「人生の質」などと訳されるQOL。自分の人生は自分で決める。たとえそれが愚行であっても。人生のゴールがチラつき始めた今自分はどんな幕引きをしたいのか、そしてそれをどうやって家族に伝えるか、これが重要。なぜならいくら個人の権利を主張しても、人間は「関係性」を切り離しては生きられないから。徘徊癖がある認知症老人が徘徊中に転倒し骨折、その後家族はリハビリを望まなかったという話は実際に直面したことがある。コレは本当に難しい。2024/01/06
しょうじ@創作「熾火」執筆中。
24
【2巡目】「生老病死」を、QOLという観点から読者とともに考えていこうとする、生命倫理学者の著。全6章。「自己決定」が伝えられないような状況の下で、当事者のQOLは確保しうるのか、そのことをどう考えていってらいいのかという、医療技術が進んだ時代ゆえの重い問いかけを投げかけてくる「たましいの練習問題」集とも言える本だと思う。同一シリーズに、この筆者のものが収められているので、それも読んでおきたい。難しい問題ではあるが、「明日はわが身」。(3/12)2018/03/10
GELC
22
健康寿命をいかに保つか、そして、どのようにして満足死を迎えるか。長期的なテーマで、今のうちから意識が必要と感じる。本人が在宅看取りを希望していても、いざ事が起こると看取り搬送が行われてしまう実態…非常に難しい問題である。日ごろから周囲の人と話し合うことは大切だが、世間体を意識したり、常識に凝り固まった人が居ると、啓発は困難である。本書の最後にあるように、プロに頼むのことも一つの選択肢として覚えておきたい。2025/09/07
タルシル📖ヨムノスキー
22
医療・介護業界だけでなく、日常生活でも耳にするようになったQOL。「人生をよりよく生きるために」とか、「人生の最後をその人らしく終わらせるために」…。〝生きる〟、〝生かされる〟…。もし自分が自分の意思を伝えられなくなったら。この本に出てくる様々な事例を読んで、終幕に向けてのこれからの人生について、改めて考える機会となりました。まずは自分がどうしたいのか、きちんと考えて、家族と話をすることから始めようかと。医療介護現場の方は必読の一冊だと思います。2019/03/27
ザビ
17
とても平易な文だけど、とても難しい問いかけの続く本だった。「病気を診て人を見ない。私という人の価値観、人生観を無視してでも治療すべきなのか」「親といえども我が子のQOLを決めていいのか」「どこまでが自然でどこからが過剰な医療介入になるのか」治療=正しい道という価値観に、人生には違う幸せもあるよと提示してくれている。普段は気づかないけど生きることの深淵って実際底無しだなと。「生きることの意味と価値について問い続けると我々は狂ってしまう。なにしろ客観的に実在するものではないから」フロイトの言葉がとても印象的。2023/05/31