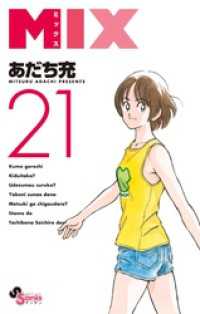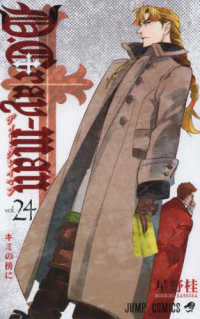出版社内容情報
親子や友人、学校や会社など固定的な関係も「一時的協力理論」というフィルターを通すと、違った姿が見えてくる。そんな社会像やそこに見いだせる可能性を考える。
内容説明
凝り固まって息苦しいように感じられる人間関係や社会も「一時的協力理論」というフィルターを通すとちょっと違った成立の姿が見えてくる。そんな社会の像やそこで考えられる可能性を想像してみよう。
目次
第1章 「無縁社会」って本当ですか?(無縁社会という捉え方;つながりのきっかけが変わってきた;無縁社会説が見逃していること)
第2章 「一時的協力」で考えてみよう(一時的協力理論とは何か;人と人との協力のあり方;協力に協力してくれる存在)
第3章 集団・組織での一時的協力とは(一時的協力はいつも不確か;協力を持続可能にする工夫;集団における一時的協力の見直し)
第4章 一時的協力理論がひらく可能性(ほころびだらけでも大丈夫な社会;協力しないことの意義;集団の存在意義を獲得する)
著者等紹介
森真一[モリシンイチ]
1962年生まれ。神戸市外国語大学卒業後、関西学院大学社会学部卒業。同大学院社会学研究科博士課程修了。博士(社会学)。現在、追手門学院大学社会学部社会学科教授。専門は理論社会学、現代社会論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
コウメ
66
本書はテーマとして「社会は、人々が一時的に協力することでなりたっている」という「一時的協力」でなりたっていることに注目した内容。その中で「無縁社会」なのか「多縁社会」のどちらかということ。昔の「縁」関係性や現在のインターネットが登場してからの「縁」関係性2019/11/26
よこしま
33
一時的協力理論◆何を言わんとするのかは分かりますが、【タイトル≠内容】のため、中高生は戸惑うのでは。いきなり無縁社会で、友達の話しがあまり出てこないのは、如何なものでしょうか。◆確かに縁というエリアが薄く広くなってしまいました。冒頭の言葉は難しく感じますが、分かりやすい箇所も。中学に上がると虐め・不登校・自殺が増えますが、小学校と中学校の教師が相互に行き来することは良い一時的協力です。子どもたちの不安などを、別グループだった教師陣が同一化することで除去し、問題が激減。◆共創という思考が重要です。2015/09/07
る*る*る
17
他も読んでる最中、今年初感想はこの難しい一冊…>_<… 私には難しかった〜図書館返却ラックで目が合い、題名借り★無縁社会・一時的協力理論…難しい‼︎ 分かった部分『普段私たちは、相手を尊敬していることを互いに表現することによって、平穏に生活できている。そういう協力をしあっている。』です(^-^)平穏に過ごしたい今年。周りの良いところ、嬉しく感じたことなど声に出していこうっと♪2015/01/07
calaf
14
社会を支えているというか社会の基盤となっているのは、人間同士、人間と動物、あるいは人間と物との間の一時的な協力関係だというのが著者の考え。言葉だけ聞いてもなるほどねぇと思ったのですが、そこからいろいろ発展も考えられるようです。2014/12/22
ochatomo
13
社会学は「社会とは何か」という問いに対する決定的な回答を出せていないのだそうだ 著者は境界性からヒントを得た「一時的協力」を提唱 等価・均衡・対等のルールから成り、主客の共創や離脱の可能性など、結んでほどくノットワーキングとする 2014刊2023/05/03