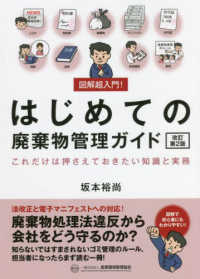出版社内容情報
名画に隠された豊かなメッセージを読み解き、絵画鑑賞をもっと楽しもう。確かなメソッドに基づいた、新しい西洋美術史をこの1冊で網羅的に紹介する。
内容説明
名画にこめられた豊かなメッセージを読み解き、絵画鑑賞をもっと楽しもう。ヨーロッパの中高生も学ぶ、確かなメソッドをベースにした新しい西洋美術史の教室へようこそ。
目次
第1章 美術史へようこそ(美術史とはなにか;なぜ美術を学ぶ必要があるのか ほか)
第2章 絵を“読む”(記号としてのイメージ;イメージとシンボル ほか)
第3章 社会と美術(社会を見るための“窓”;トビアスの冒険―ルネサンスを開花させた金融業 ほか)
第4章 美術の諸相(美的追求と経済原理;パトロンのはなし ほか)
第5章 美術の歩み(エジプトとメソポタミア;エーゲ文明と古代ギリシャ ほか)
著者等紹介
池上英洋[イケガミヒデヒロ]
1967年広島県生まれ。東京芸術大学卒業、同大学院修士課程修了。恵泉女学園大学人文学部准教授を経て國學院大學文学部准教授。専門はイタリアを中心とする西洋美術史・文化史。レオナルド・ダ・ヴィンチをはじめ、中世からバロック時代の芸術の分析を通じて、社会構造や思想背景を明らかにする方法に定評がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まつこ
61
西洋美術初心者には最適な一冊。少しばかり世界史の知識は必要ですが学校でサボってた私でも大丈夫でした。この本のいいところはただ歴史を連ねるだけではなく、まず絵画の勉強法から入門できるところです。何をどう見て、何に繋げていくか。そういう背景が見られるようになるための導入書です。個人的には17世紀のオランダに興味を持ちました。ちくまプリマー新書はヤングアダルトだけでなく初心者にも有難いです。最後には推薦文献の案内もあり、造形を深めるのに役立ちそうです。2014/10/14
Nobu A
57
池上英洋著書初読。12年刊行。著者は東京造形大学教授。美術史学者。非常に印象に残る一冊。美術史とは何かから始まる。考えたこともなかった。その意義を指南。図解解釈学(イコノロジー)を援用し「成立過程とその背景」と「社会的・精神的背景」で歴代の美術品を解説。美術鑑賞の入門書として素人には十分。おわりにヨーロッパの美術館では学生達が車座で絵の前に立つ先生と議論をしている光景をよく目にするとある。日本とは何故こうも違うのか。大学の講義でしか美術史を学ばない日本。芸術後進国を痛感。教養の一部として美術教育が必要。2024/08/25
molysk
53
美術史では、「なぜそのような作品がその時代にその地域で描かれたのか」、「なぜそのような様式がその時代にその地域で流行したのか」といった点を思考する。本書では、絵の持つ意味の読み解き方と絵が描かれた背景の考察、美術作品がもつ社会的機能の調べ方、「技法」と「主題」という美術作品の側面とパトロンとの関係、古代からルネサンス、現代に至る美術の歩みが述べられる。ごく最近に至るまで識字率は低く、大衆に対する最大のメディアは絵画であった。頭蓋骨は死、鍵を持つ男はペテロ、といったコードを知れば、絵画鑑賞を深く楽しめる。2019/09/06
ホークス
48
2012年刊。社会や文化と共に変化してきた美術を、独自の解釈を交えて分かりやすく解説する。知識は必要だが、知識で人を格付けするなど下品。ただ好奇心のまま探究するのが楽しい。著者は美術史を通して「自分を知り、人間を知る」事を読者に勧める。私は勉強になる事が多かった。スーラ等が点描画を描いたのは、明るさを得る為だと今更ながら理解できた。17世紀の、貧乏人や障害者が食べたり笑っている絵は、金持ちが自らの慈善行為を神にアピールする為に描かせた。救い難いけど、自分の独善や強欲を省みる意味では聖画なのかも知れない。2022/02/19
inami
38
◉読書 ★3.5 これまで絵画に関する本は原田マハさんの作品を中心に10冊以上読んではいるが、本書に書かれていることにについては知識が不足していた。絵は昔の”識字率”が低かった西洋世界で、大衆に何かものを伝えるという機能(言語の一種)を持っていた。また、絵の買い手(パトロン)は貴族や教会が多く、そのため残っている作品も宗教画や肖像画等が多い。フェルメールの作品は風俗画がほとんどだが、買い手が商人で売れるシステムができていた・・彼のゴッホでさえ生前に売れた作品は一点のみ、絵の世界はすばらしくも実に厳しい・・2019/11/02