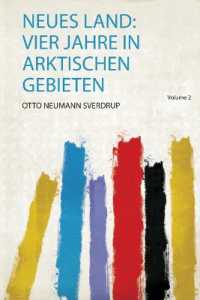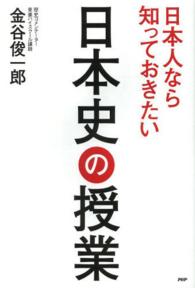出版社内容情報
人はなぜ小説を読むのか、なぜ書くのか。
小説はなぜあるのか。
しかも古今東西数えきれないほどの作品が書かれている。
それは小説という表現形式が大いなる可能性を秘めているからだ。
小説好きも、そうでない人にも知ってほしい
小説の計り知れない可能性について。
内容説明
小説はなぜあるのか。しかも古今東西数えきれないほどの作品が書かれている。それは小説という表現形式が大いなる可能性を秘めているからだ。小説好きにも、そうでない人にも知ってほしい小説の計り知れない可能性について。
目次
第1章 小説にはなんでもできる(技術篇)
第2章 小説にはなんでもできる(内容篇)
第3章 小説は道徳にとらわれない
第4章 小説は人間の多様性を描きわける
第5章 小説はダメな人間を輝かせることができる
第6章 小説は空想を描ける
第7章 小説は時代を描くことができる
第8章 小説は理想を託すことができる
第9章 小説は美を追求することができる
第10章 小説は人を励ますことができる
著者等紹介
藤谷治[フジタニオサム]
1963年生まれ。小説家。日本大学芸術学部映画学科卒業。会社員を経て、東京・下北沢に本のセレクトショップ「フィクショネス」を経営。『いつか棺桶はやってくる』が三島由紀夫賞候補、『船に乗れ!』(2010年)本屋大賞第7位。『世界でいちばん美しい』で織田作之助賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
27
小説はなぜあるのか。古今東西数え切れないほどの数が書かれている小説という表現形式が秘める大いなる可能性について考える1冊。書き手はどんな風にでも書ける自由があって、読んだ読者もそれをどう受け止めるかという自由があって、その時代ごとの状況や道徳といった限界もある中で、その作をいかに描くのか。登場人物に成長や事件といった状況をいかに与えるかによって、ダメな人間でも魅力的な存在として描くことができたり、空想の世界を描いたり理想を託したり、励ますことができる小説の様々な可能性をわかりやすく教えてくれる1冊でした。2024/11/05
タルシル📖ヨムノスキー
26
読書が趣味になって8年。気がつけば再読含め2500冊以上読んでいて、そのほとんどが小説。今まで〝小説って何だろう〟なんて考えたことはありませんでした。考えてみれば小説ってすごい。読めば頭の中にその情景が浮かんでくるし、誰かの心情を追体験も出来る。海だって山だって宇宙にだって行ける。音楽だって鳴り出す。読んで落ち込むことも背中を押してくれることもある。古今東西の名著を例に挙げながら、小説の持つ無限の可能性について解説している本。紹介された本で手に取ってみたいのは、カレルチャベックの〝サンショウウオ戦争〟。2025/10/06
kana
24
本屋で立ち読みしてたら、これってもしかして、私が大好物の、文学作品の魅力を素敵な切り口で捉え直せるブックレビュー本では!?思い、また、文章も一文一文が平易で読み心地がよくて、気付いたらレジへもっていっていました。実際「ドラキュラ」「うつほ物語」等、新たな視点で魅力を知ることができて、いつか読みたい本がまた増えました。小説は読んでも目に見えて役に立たないけど意味はあるといった日々思うことが言語化されていたのもよきでした。小説は「人を励ます」ことができるというのが特に深いです。2025/01/19
スプリント
15
小説の可能性と読書の役割について丁寧に論じられています。 納得できる点も多いですが普段読書をしない人はどのような受け止めて方をするのか気になります。2025/01/14
frosty
14
面白く読める本だったように感じる。新書なので、腰を据えて読み進めなければ、と覚悟して読み始めた本だったが、不思議とスルスルと読み進めてしまえる本だった。この著者のようにそれこそしっかりと腰を据えて、「小説にできること」を考えてみると、小説はとても多くの可能性があり、とても自由度の高い表現媒体なのだな、と改めて理解できたように思う。その中でも特に、小説に何ができるか、一番印象に残ったのは、「人を励ますことができる」というものだったな、と個人的には大切に感じた。私もきっと励ませ続けられてきたうちの一人だろう。2024/11/27
-
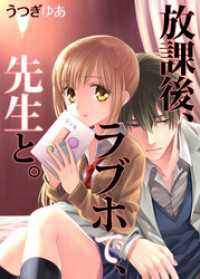
- 電子書籍
- 【フルカラー】放課後、ラブホで、先生と…