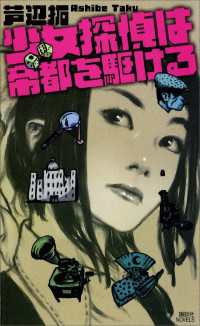出版社内容情報
世界には、「貧富の差」のない共同体や、学校に行かずそもそも「教わる」という概念もない社会が存在する。常識を常識をひっくり返して「そもそも」を問う思考法には、問題を定義し直し、より本質的な議論に導く力があります。学校教育や貧富の格差、心の病など、身近で大きな社会・環境危機に人類学で立ち向かう一冊。
【本書で扱う一例】
ヘヤー・インディアンは「教わる」という概念を持たない
⇒学校ってなぜ行くの?そもそも学ぶって何?
プナンは獲物もお金もみんなでシェアして貧富の差がない
⇒格差や権力はそもそもなぜ生まれるの?
ひっくり返して考えた時、問題の根本が見える。
内容説明
常識をひっくり返して「そもそも」を問う思考法には、問題を定義し直し、より本質的な議論に導く力がある。学校教育や貧富の格差、心の病など、身近で大きな社会・環境危機に人類学で立ち向かう。
目次
序章 人類学でひっくり返すとはどういうことか?(「精神の危機」によって生まれた人類学;『ひっくり返す人類学』とは何か? ほか)
第1章 学校や教育とはそもそも何なのか(私の「お稽古ごと」時代;ピアノ教室の未知の世界 ほか)
第2章 貧富の格差や権力とはそもそも何なのか(世界と日本における貧富の格差;貧富の格差のないプナン社会 ほか)
第3章 心の病や死とはそもそも何なのか(働きすぎやうつ病をめぐる私たちの日常;うつ病や心の病のない社会 ほか)
第4章 自然や人間とはそもそも何なのか(自然と人為という枠組み;人間から分け隔てられる動物 ほか)
著者等紹介
奥野克巳[オクノカツミ]
1962年、滋賀県生まれ。立教大学異文化コミュニケーション学部教授。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
樋口佳之
ノンケ女医長
よっち
tsu55
ta_chanko