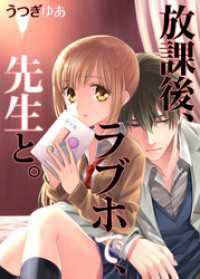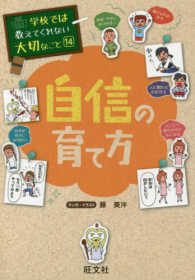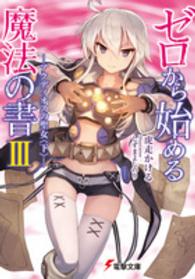出版社内容情報
調査は聞くこと、分析は考えること、理論は表現すること。この社会のことをみんなで考えてなんとかしたい人のための、三つの基礎が身につく入門書。
内容説明
社会学は、みんなにとって大事なことについて、しっかりしたデータにもとづいて考え、それを表現する営みです。この社会の複雑な問題をなんとかしたいと思ったら、社会学があなたの力になります。
目次
第1章 世界は意味に満ちあふれている―やっかいな問題としての社会
第2章 社会学って何だ?―みんなで規範の物語を作るいとなみ
第3章 聞くことこそが社会学さ―対話的な社会認識としての調査
第4章 社会学は泥臭い分析技法を手放さない―圧縮して考える
第5章 なんのための理論?―表現の技法としての理論と物語
第6章 みんなソシオロジストになればいいのに―人びとの共同のいとなみとしての社会学
著者等紹介
宮内泰介[ミヤウチタイスケ]
1961年生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。博士(社会学)。北海道大学大学院文学研究院教授。専門は環境社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
57
社会学には以前から関心があり、手に取った。帯にあるとおり、調査で聞き、分析で考え、理論で表現する。これは、社会学に留まらないと思う。自分の身近なところでは、地域における諸活動が当てはまる。自分なりの視点で、課題を考え、周囲の声を聞き現状を調べ、今後の取り組みを理論立てて考えること。しかも、地域住民の現状(暮らし)をベースにスタートすること。答えは、いろいろあり得るし、時間と共に変わりうる。すっと馴染める1冊。2025/05/27
よっち
26
社会の複雑な問題をなんとかしたいと思った時に力になってくれる社会学。しっかりしたデータにもとづいて考え、それを表現する方法をわかりやすく解説した1冊。社会学をはじめるための「調査は聞くこと」「分析は考えること」「理論は表現すること」という3つの基礎を紹介しながら、複雑でやっかい問題としての社会のこと、社会学とはどういう学問なのか、対話的な社会認識としての調査、同時並行させる泥臭い調査技法と分析・数値化や圧縮、言葉で表現するということや、人々の共同の営みとしての社会学がとてもわかりやすく紹介されていました。2024/07/23
武井 康則
14
社会学は何を対象としているのか、研究方法はフィールとワークが中心。どんな理論があったかなど、ごく簡単に入門書として書かれている。そのまま大学一回生の教科書として使えそうな内容。すべてに目を通している分、個別の内容に立ち入らず、すべてはこの本から出発しようという立ち位置。プリマー新書というコンセプトに忠実だが、副題は疑問。やや誇大広告では。複雑な社会を叙述する技法とすべきでは。2024/06/22
かおりん
6
社会学の入門書。私は医師なので社会学にはあまり馴染みがなかったのだけれど、学生時代から社会医学分野には興味があって。いま臨床の傍らあらためて社会医学を勉強しているところなので、この本を手に取ってみました。すごく曖昧な認識だった「社会」というものが、まさに霧が晴れたように定義された感覚。社会学は規範をもとに成り立っていて、人の営みの中で流動的に変わっていくものである。社会学は対話しながら問題を捉え直し、解決し続ける学問。私も実践したい!2025/10/12
イシコロ
6
ここで示される社会学は、絶対普遍の探究は一旦諦めており、その点で学問的でないと感じた。 一方では対話を続け暫定での妥当性を更新続ける営みは科学的だと感じた。 公私の目線を言ったり来たりすることもまた社会学だ理解した。そうであれば自分史を探求することによっても社会学が可能なのか。2025/01/28