出版社内容情報
沖縄の基地問題を理解し、その解消を目指すためには、まず、沖縄が日本に併合された経緯やその後何度も本土のために犠牲になった歴史を知らなければならない。
内容説明
沖縄になぜ基地が集中しているのか?基地問題を理解し、その解消を目指していくためには、沖縄が日本に併合された経緯や、その後何度も本土の犠牲になった歴史を知らなければならない。琉球処分、人類館事件、沖縄戦、アメリカによる統治、基地問題…。本土と沖縄の関係を読み解くための大事な一冊。
目次
第1章 沖縄の歴史(球琉処分;人類館事件;アジア太平洋戦争と沖縄)
第2章 構造的差別とは何か(沖縄戦後に「戦後」は来たか;基地の島・沖縄)
第3章 沖縄から問われる「構造的差別」(沖縄からの「県外移設」論;新たな「沖縄戦」の危機)
対話 沖縄へのコロニアリズムについて―知念ウシ×高橋哲哉
著者等紹介
高橋哲哉[タカハシテツヤ]
1956年生まれ。哲学者。東京大学教養学部教養学科フランス科卒業。同大学院哲学専攻博士課程単位取得。東京大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
116
帯に「琉球処分、人類館事件、沖縄戦、アメリカによる統治、基地問題…」とある。でも、そんな歴史的事実を知ってほしいだけの一冊ではない。当然それらを理解した上で、沖縄の人たちが何を考え何を感じているかの本当を知っておきたいと、著者は訴えている。巻末の対談で知念ウシさんは「沖縄の現状は日本の植民地支配だと思う」と断言する。軍事基地の不均衡な集中は「人種主義(レイシズム)の現代的形態」だとも。琉球独立論や琉球先住民族論が沸き起こるほど沖縄の人たちが追い込まれている現状を、私たちは、どれだけ理解できているのだろう。2024/08/01
アキ
104
沖縄といえば、青い海、リゾート、美味しい料理とステレオタイプに思い浮かべるが、沖縄に住んでいる人から本土人はどう映るのか?明治政府の琉球処分、土人発言、太平洋戦争での捨て石としての沖縄、更に天皇のマッカーサーへのメッセージなど沖縄の歴史は日本本土を守るための防衛線であり、日本の人口の約1%の土地に米軍基地の約7割を押しつけている事実に見て見ぬふりをしている。無意識の植民地主義と指摘する社会学者がいる。沖縄を思いやるなら、基地を本土にもって帰るのが一番の連帯ではないかという声に黙るのを「権力的沈黙」と呼ぶ。2024/05/18
Nobuko Hashimoto
37
沖縄本を読む月間延長。非常にわかりやすくまとめられている。もともと別の国だった琉球を併合し、戦争中は本土への攻撃を遅らせる捨て石とし、戦後、特に「復帰」後は米軍基地の大半を負担させてきた事実と、その根底には植民地主義があることをきっぱりと説く。巻末の知念ウシ氏との対談では、「沖縄大好き♡」に潜むオリエンタリズムを指摘。戦中の島田叡知事をヒーローに祀り上げる動き(2本の映画)に対しては「ヤマト側の一種の文化戦略である」という評もあり。文章は柔らかいが、「本土」の人間の見ないふりに鋭く切り込み思考を促す。2025/08/03
kan
30
これは高校生に薦めたい。勤務校図書館の沖縄修学旅行棚の一冊だが、沖縄戦や基地問題等についてひととおり学んだ後に、自分の態度を振り返らせ、考え方を揺さぶる良書。特に知念ウシさんとの対談が示唆に富む。「本土」の人間の無意識の植民地主義による欲望、権力的沈黙、移住者ロマンへの批判は、沖縄の歴史や痛みや怒りや願いをすべて引き受けている「ウチナーンチュ」ならではの正直な思いだと重く受け止めた。安易な「沖縄大好き」の根底にある無意識のコロニアリズムが人を傷つけ、構造的差別と対立を深化させるという視点は生徒に伝えたい。2024/08/11
GELC
20
沖縄を本土の物理的な盾、政治的バッファーとして使う思想は松陰まで遡る。その流れを汲む政治家が牛耳る限り、この構造キープが絶対の路線だと理解した。平和憲法は尊いものだと信じているが、沖縄に犠牲を強いているという認識は無く、ドキリとさせられた。また、日本全体では沖縄は少数勢力なので、多数決を取ると今の体制支持者が圧倒的多数になるのは、民主主義の限界を突きつけられた思いだ。安保が必要なら本土も相応負担をということは至極当然の理論。本土の人間が、不当に優位な立場にあることを認め、利権を放棄する勇気、覚悟が必要。2025/07/19
-
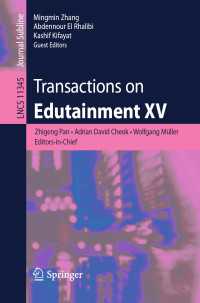
- 洋書電子書籍
- Transactions on Edu…







