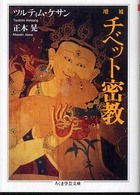出版社内容情報
完璧なる優美、子どもの無垢、美の残酷と壊れたような狂気、楽しさと同居する寂しさ――モーツァルトとはいったい何者だったのか? 天才の真実を解き明かす。
内容説明
完全なる優美、子どもの無垢、美の残酷、壊れたような狂気、死の臭い、そして楽しさと同居する寂しさ―目まぐるしく濃淡が変化する人間心理の綾を音で描くことができた音楽史上ただ一人の作曲家、モーツァルト。天才少年の殻を自ら打ち破り、初のフリー芸術家という革新的な活動を繰り広げた天才の真実とは?
目次
モーツァルトの比類なさはどこに?
「天才君」の栄光と悲惨
「ある」と「なる」―天才の二つのありよう
失意は天才少年の宿命
教育パパの呪縛は結婚で断つ
「天才」とは何?
フリーになるということ
芸術家と実人生
美の冷酷さについて
実存の不安と「まあこんなものか…」の希望
「ところで」の奇跡
流麗さについて―モーツァルトの作曲レッスンを受ける
晴れた日のメランコリー
モーツァルトは神を信じていたか?
幸福な阿呆に神は宿る
著者等紹介
岡田暁生[オカダアケオ]
1960年京都生まれ。音楽学者。京都大学人文科学研究所教授。『オペラの運命』(中公新書)でサントリー学芸賞を受賞。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
卵焼き
77
モーツァルトの人柄、背景がよくわかり、面白かった。2021/11/05
trazom
72
流石に岡田先生。単なる伝記ではなく、モーツァルトの音楽に踏み込んだ一冊であることは、見出しを見ればわかる。「真善美をあざ笑う」「「ところで」の奇跡」「晴れた青空の諦念」「モーツァルトは神を信じていたか」など、作品の本質に関わる問題提起がなされ、岡田先生の見解が示される。ウィーン時代初期のピアノ協奏曲の評価や「ポストホルン」の解釈など、私の考えと異なる部分はあるが、でも、「かなしさは疾走する」(小林秀雄)のようなレトリックで煙に巻くのではなく、具体的な楽曲の例を示して音楽と向き合う姿勢は、とても勉強になる。2020/10/20
1959のコールマン
63
☆4。ちくまプリマ―ということですこし遠慮したのかな?もう少し突っ込んで書いて欲しかった。やはりクラシック畑の人だとここまでが限界なのかな。「ポピュラー音楽なら(ハードロックは別として)「怒」は抜きで、「喜哀楽」に限定されているといっていいかもしれない」p140なんて言ってるし・・・(ラップ、ヒップホップや古くはフォーク、シャンソンなんかどうなんだ)。やはりポピュラー畑の人がモーツァルトを書いて欲しいな。希望はブラック・ミュージック系の人。読んでいるとモーツァルトとの共通点が結構ありそうだ。2020/10/31
ジョンノレン
48
著者本連続読みその1。冒頭から小林秀雄やキルケゴールのモーツァルト感についての違和感に加え、指揮者井上道義氏のフランクで肩の力の抜けたインタビューで、立教時代から巨人入団した頃まで長嶋茂雄氏がモーツァルトを愛聴していたエピソードが紹介されたりと、ぐんぐん吸い込まれる。モーツァルトの天才性や境遇についてはシェーンベルクと対比されるなど、意表をつく展開に目が離せない。勿論想定内の内容も多々ながら、その先というかその背後まで抉り出しエキスパートの面目躍如。オペラ解説本としても秀逸。2023/10/16
まこみや
38
楽器も演奏できないし、楽譜もよめない。音楽理論についても何も知らない。ただ感覚だけで音楽を聴いてきた。そんなないないづくしの私のような者に、近代へと社会の体制と人々の意識が変化する中で、モーツァルトの「天才」を、作品に即して実にわかりやすく教えてくれた。平明で説得力のある文章だと思う。因みにピアノ協奏曲は、これまで吉田秀和さんお薦めのフリードリッヒ・グルダの演奏(最初に買ったモーツァルトの協奏曲だった)を愛聴してきたが、バレンボイム/クレンペラーの25番やカサドゥシュ/セルの27番を早速聴いてみたい。2021/08/27