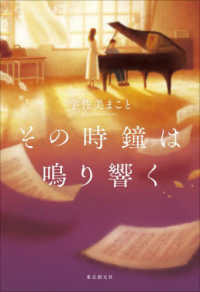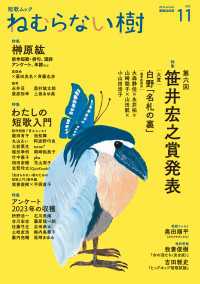出版社内容情報
改憲論議、格差社会、日米関係、メディアと世論……。いま議論になっている問題のはじまりは昭和にあった! 戦前・戦時下・戦後のダイナミックな歴史を一冊に。
内容説明
開戦までの駆け引き、戦時下の生活、憲法改正の舞台裏、焼け跡からの復興、アメリカとの交渉、新メディアの誕生…、ここが時代の転換点。日本史の中で最も重要!昭和を知れば、論点がもっとみえてくる。
目次
第1章 帝国憲法と日本国憲法のつながり
第2章 政党政治をめぐる三つの疑問
第3章 戦前と戦後に共通する協調外交
第4章 安全保障政策
第5章 格差の拡大から縮小へ
第6章 絶え間なく起きる昭和の社会運動
第7章 文化が大衆のものになる
第8章 メディアをめぐる問題の起源
著者等紹介
井上寿一[イノウエトシカズ]
1956年生まれ。一橋大学社会学部卒。同大学大学院法学研究科博士課程単位取得。学習院大学学長などを歴任。現在、学習院大学法学部教授。法学博士。専門は、日本政治外交史。主な著書に『危機のなかの協調外交』(山川出版社、吉田茂賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Aya Murakami
95
他館図書館本 昭和は昭和でも戦前戦時中パートと戦後パートにわけて両者を比較しています。社会運動が民衆とうまく連動せずに機能不全に陥ったり、人命や生活が軽視されたりということは戦前戦時中も戦後も意外と変わらないのでは…?と読み終わりました。変化しているようで変化してない昭和64年間というのは結構意外な話でした。2021/03/07
かんがく
15
同じプリマ―新書の「はじめての明治史」と同じく、平易かつ最新の研究成果を盛り込んでいて入門書として最適。各章で憲法、政党政治、外交、安全保障、格差、社会運動、大衆文化、メディアをそれぞれテーマとして、断絶が強調されがちな戦前戦後を通して「昭和」として扱っている視点が良い。2020/11/01
月をみるもの
13
日本国憲法は、第日本帝国憲法の改訂版であるということが有名な「前文」の、さらに前にある文章を読むとよくわかりますね。 "朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる" http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm2020/09/12
keint
11
昭和史をいくつかのトピックごとに扱い、戦前・戦中と戦後の連続性を意識して解説されている。レーベル自体が中学生を対象としているため、中学社会の歴史の教科書の記述を引用し、それに対して研究の動向等を補足していくというスタイルが本書の他の昭和史系新書との違いであると感じた。青少年向けとはいえども、鳩山一郎内閣における新生活運動や農本主義者の山崎延吉など初めて知ったことも多いため、昭和史についてある程度知識がある人でも参考になると思われる。2020/10/22
バルジ
6
初学者のみならず昭和史を多少は勉強している人間でも十分楽しめる1冊。同じ著者の『論点別 昭和史』との重複も多々あり尻切れトンボとなる章もあるが、トピック的には過不足をあまり感じず纏められている。本書では戦前・戦後を断絶したものせず政治・外交・文化等を一つの筋として提示する。中でも興味深いのは戦前の国民精神総動員運動が名称を変えそのままの姿で「新生活運動」と銘打って展開された点であった。結果的に戦前と全く同じく単なる「精神運動」に終わったものの、上からの生活統制に関しても戦前戦後を貫く思考があるのは面白い。2021/03/21