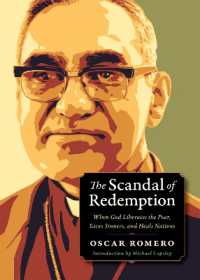出版社内容情報
マナーや陰口等、他者といる際に用いる様々な技法。そのすばらしさと苦しみの両面を描く。「生きる道具」としての社会学への誘い。解説 三木那由他
内容説明
わたしたちが日々意識せずにおこなう「他者といる技法」。そのすばらしさや正しさだけでなく、苦しみや悪も含めて、できるかぎり透明に描くにはどうしたらよいか―。思いやりとかげぐち、親と子のコミュニケーション、「外国人」の語られ方、マナーを守ることといった様々な技法から浮かび上がるのは、“承認と葛藤の体系としての社会”と“私”との間の、複雑な相互関係だ。ときに危険で不気味な存在にもなる他者とともにいる、そうした社会と私自身を問いつづけるための、数々の道具を提供する書。
目次
序章 問いを始める地点への問い―ふたつの「社会学」
第1章 思いやりとかげぐちの体系としての社会―存在証明の形式社会学
第2章 「私」を破壊する「私」―R・D・レインをめぐる補論
第3章 外国人は「どのような人」なのか―異質性に対処する技法
第4章 リスペクタビリティの病―中間階級・きちんとすること・他者
第5章 非難の語彙、あるいは市民社会の境界―自己啓発セミナーにかんする雑誌記事の分析
第6章 理解の過少・理解の過剰―他者といる技法のために
著者等紹介
奥村隆[オクムラタカシ]
1961年徳島県生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。東京大学文学部助手、千葉大学文学部講師・助教授、立教大学社会学部教授を経て、関西学院大学社会学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ジョンノレン
読書一郎
Kano Ts
はとむぎ
ぷほは